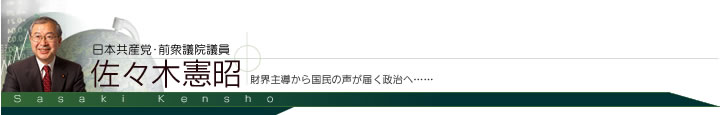東海での活動
東海での活動 − 政府への要請、教育、住民生活、災害、医療・介護・障害者・年金、愛知県
【12.02.10】愛知県の皆さんと政府要請
2012年2月10日、佐々木憲昭議員は、愛知県の皆さんとごいっしょに、政府要請を行いました。
この要請には、河江明美・東海ブロック比例予定候補、本村伸子・参院愛知選挙区候補、西田とし子ひさし・小選挙区予定候補、石川ひさし・小選挙区予定候補、山口きよあき・名古屋市議、さはしあこ・名古屋市議、岡田ゆき子・名古屋市議、岡本守正・碧南市議、下島良一・碧南市議、山口きよあき・碧南市議、山内さとる・半田市議、内藤とし子・高浜市議、わしみ宗重・高浜市議、根本美春・豊田市議などが参加しました。

国土交通省や総務省などに対し、東日本大震災で多くの防波堤が沈下・崩壊した事実などを受け、名古屋港、衣浦港、三河港と沿岸部の防災対策を強化、石油コンビナートの防災対策の強化を求める要請を行いました。
この要請書は、愛知県内の沿岸部の自治体の議員の皆さんのご意見を寄せられたものです。
また、保育所の待機児童解消や児童扶養手当の運用の改善の政府要請、海上コンテナの安全輸送に関する関する聞き取り、高浜市、名古屋市の競艇の場外舟券売り場建設問題で聞き取り・地元住民の要望書提出なども行われました。

政府の回答については、本村伸子・参院愛知選挙区候補のホームページをご覧ください。
リンク【のびのびレポート】愛知県内沿岸部の津波防災対策、石油コンビナートの防災対策、保育所の待機児童解消、児童扶養手当の運用の改善を政府交渉/海上コンテナの安全輸送に関する関する聞き取り/高浜市、名古屋市の競艇の場外舟券売り場建設問題で聞き取り、地元住民の要望書提出
名古屋港、衣浦港、三河港及び愛知県内沿岸部の防災対策の抜本的強化に関する要請
東日本大震災では、多くの防波堤が津波や高潮の被害軽減に一定の役割をはたしつつも、その多くが沈下したり崩壊したりしてしまいました。埋立地域での液状化による被害も甚大なものがありました。名古屋市および愛知県内沿岸部の自治体は、東海、東南海、南海等の連動地震が想定されているだけに、東日本大震災の教訓をふまえ、防災に強い街づくりをすすめることが急務となっています。
名古屋港においては、高潮防波堤があるものの老朽化しており、巨大地震にともなう液状化によって大きく沈下するとの予測がされるなど、大規模な耐震補強工事が求められています。
また、名古屋市では、ゼロメートル地帯である港区・南区をはじめ、6行政区で津波避難ビルの指定を開始し、これまでに498棟(2012年1月27日現在)が指定を受けました。
しかし、多くの住民を避難させ得る一定の高さと構造をもった施設は、まだまだ少ないのが現状です。臨港地区での避難ビルについては、特に指定が遅れています。
名古屋市としては一定の耐震性能を有する学校や住宅の屋上の整備に取り組んでいるものの、多額の費用が必要になっています。これら費用に関する制度的保障はありません。
いかなる巨大地震があろうと、津波による被害を最小限におさえることのできる港湾隣接地域の防災対策を抜本的に強めるため、以下の内容を要請します。
- 名古屋港高潮防波堤について、東日本大震災の津波防波堤等の被害状況と最新の研究成果を踏まえ、予想される南海トラフを震源とする海溝型巨大地震とそれによる津波に対応できるよう、早急に機能強化をはかること。(国土交通大臣)
- 既存及び新築の建築物に、津波避難ビルとしての機能を付加する設備投資に対しての助成制度を創設すること。臨海部などでは建築許可の基準のひとつに津波避難ビルの機能を有することをもりこむなど、津波避難ビルの機能を有する建物を増やす施策を強化すること。(国土交通大臣)
- 港湾地域での緊急避難場所となるような津波避難ビル、または津波避難タワーの設置及び確保を港湾管理者に義務付けるとともに、建設への補助制度を設けること。(国土交通大臣)
- 重要港湾に指定されている衣浦港及び三河港および愛知県内沿岸部についても前3項に準ずる措置を講ずること。(国土交通大臣)
- 中央防災会議で結論が出された後に、愛知県が防災計画の見直しを行い、その後に各自治体が防災計画を策定することになっており、対策が遅れている。東海、東南海、南海等の連動地震、マグニチュード9、原発事故を想定し、国が早急に計画をまとめること。(防災担当大臣)
- 避難経路の確保、公共施設や高層階の民間施設を緊急一時避難所として協定を結ぶことなど適切で迅速な対策を講じるよう国が地方自治体を指導すること。(防災担当大臣、総務大臣)
現在ある堤防内部の空洞化調査、高さの見直し、補強工事、位置の適正化などへの国の予算を増額すること。(国土交通大臣)
- 新日鉄など臨海部に立地する企業や関係企業などの港湾労働者や観光客、つり人など住民にたいする緊急避難場所の確保等、国は労働者や住民の命を守るため責任をもって指導すること。(防災担当大臣、国土交通大臣)
- 避難勧告や避難指示が出ていても港湾労働者に伝わらず、仕事を継続していたり、港湾利用者から夜間作業を求められたりする事例が名古屋港であった。港湾労働者への情報伝達と避難が確実にできるよう措置をとること。大規模災害時は、施設利用(荷役作業等)を中止させること。(防災担当大臣)
- 港湾労働者が、大規模災害時の実際の行動を想定した避難訓練ができるよう措置をとること。(防災担当大臣)
- 人の出入りの多い港湾の特徴を踏まえ、わかりやすい避難先、避難経路の標識などを設置すること。(国土交通大臣)
- 全国瞬時警報システム(J-Alert)と連動した同報無線と戸別受信機の設置補助を拡充すること。(総務大臣)
- 聴覚障がい者は、同報無線放送が聞き取れないため、緊急時の伝達方法の対策を検討すること。(総務大臣、厚生労働大臣)
- 防災無線等が停電によって使えないという事態が生じないよう万全な対策をとること。(総務大臣)
- 佐久島、日間賀島、篠島などの離島は、被災時には、ライフラインが寸断され、長期的な孤立化が想定される。避難所に太陽光発電や大型発電機の設置など対策をすすめるため、国は特段の支援策を講じること。(防災担当大臣)
- 国道一号の尾張大橋の架け替えと周辺堤防の早期整備を実施すること。(国土交通大臣)
- 災害対応時に消防力の強化が重要である。整備指針にもとづく人員の充足率を引き上げるため国は支援すること。(総務大臣)
- 合併により役場が支所になったことで、災害時の初動体制や本庁職員の支援体制が心配されている。災害時の支所等の役割はきわめて重要であり、防災体制の強化が図られるよう適切な指導を行うこと。(総務大臣)
- 避難所の整備、沿岸部の公共施設の強化、移転にたいする国の支援を充実すること。
- 災害時避難場所は、避難者のプライバシーを守ることやバリアフリーを進めることが必要であり、国は支援策を講じること。(防災担当大臣、総務大臣、厚生労働大臣)
- 避難所となった学校等で食事を提供できるよう自園、自校給食を広げるよう国が指導と援助を行うこと。(文部科学大臣)
- 福祉避難所の指定が不十分な状況であり、国の指導と援助を強めること。(厚生労働大臣)
- 民間住宅耐震改修補助制度を増額し、耐震化達成率を高めることが必要であり、国の援助を強めること。(国土交通大臣)
- 津波対策のため学校の屋上の補強工事とともに頑丈な手すりを設置するなど、緊急時に備える国の援助を強めること。(文部科学大臣)
- 津波避難場所の少ない地域及び避難場所のない地域の緊急時に備え、津波用ライフジャケットを各家庭に配布すること。自治体のそうした事業への補助制度を設けること。
- 消防署、学校、保育所、避難所はじめ公共施設が、液状化現象に耐えうるか否かの調査を進めること。これらの建築物が新築・改修する際などに液状化対策を行うエリア指定と補助を実施すること。戸建て住宅等についても同様の支援措置を講ずること。(文部科学大臣、国土交通大臣)
石油コンビナート等特別防災区域における防災対策に関する要請
東日本大震災は、東京湾の石油コンビナート地帯においても、液化石油ガスタンクの倒壊による火災や、液状化による側方流動の発生、浮屋根構造タンクでのスロッシング現象などが発生しました。
名古屋港は、港の入口にあたる一角が、石油コンビナート等災害防止法にもとづく「石油コンビナート等特別防災区域」に指定されています。地震と津波により、危険物施設が集中しているこの地域で災害が発生すれば、名古屋市の市民生活と港湾業務を含む産業活動にも甚大な影響を与えることになりかねません。
しかしながら、名古屋市域においては、省令にもとづき2017年(平成29年)までに改修が必要とされる特定屋外タンク(1000kl以上)8基のうち、すでに適合しているタンクは1基のみで、とりわけ浮屋根構造の1万kl以上のタンクは4基すべてが未改修となっています。また、この石油コンビナート地帯は、すべてが伊勢湾台風(1959年)以降の埋立地であり、地盤の液状化や側方流動による護岸のはらみ出しなども予想されます。
そこで、埋立地に造成された石油コンビナート地帯における防災対策の強化をすすめるため、以下の点を要請します。
- 特定屋外タンクの耐震改修について、省令で定めた期限を前倒しするなどして、早期に100%のタンクで必要な改修を終えること。(総務大臣、経済産業大臣)
- 個別の貯蔵施設だけでなく、地盤の安全性が問われています。企業の敷地を含めて特別防災区域内の地盤と護岸すべてについて液状化及び側方流動に関する実態を調査するとともに、有効に安全対策を講じること。(総務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣)
- 原油(LNG)受け入れ基地である伊勢湾シーバースの大規模地震など災害にたいする安全性を確保すること。検査結果を明らかにすること。(総務大臣、経済産業大臣)
待機児童問題解決のための要請
名古屋市は、昨年10月の待機児童数が1909人(うち3歳未満児1714人)と、引き続き全国最多となっています。多くの父母が子どもを保育園に入れたいと望む中、名古屋市の待機児童数は1909人となっています。一方、政府は保育所にかかる最低基準を緩和し、「子ども・子育て新システム」の導入で保育現場に市場原理を持ち込む方向に向かっていますが、それでは保育の質の低下と福祉としての保育の崩壊をもたらしてしまうのではないかという不安が広がっています。
現在の最低基準を引き下げることなく待機児童問題を解決するためには、保育に対する国と自治体の責任を明確にし、公立でも民間社会福祉法人でも保育所を抜本的に増設できるよう十分な予算措置を行う必要があります。
誰もが安心して利用できる保育制度の拡充のため、以下の点を要請します。
- 国と市町村に保育実施義務のなくなる「子ども・子育て新システム」を導入しないこと。(厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣)
- 公立保育園の建設を促進することをはじめ、認可保育園の新設とあわせて、保育所待機児童を解消できるだけの十分な予算措置を行うこと。
- 規制緩和でなく、子どもの命と安全を守れる保育環境整備のため、最低基準を抜本的に改善すること。(厚生労働大臣)
- 0才、1才児の面積最低基準を3.3㎡で整備できるようにするため、改築・整備に国の支援を強めること。名古屋市は国の指導のもとで基準に満たない現状となっていることから、特別の財政措置として、「保育環境改善事業」をほふく室整備にも活用できるよう、柔軟に対応すること。(厚生労働大臣)
- 認可保育園を増やすために国有地を貸与する際の賃貸料を無償または低廉化すること。また、同様の制度が地方自治体等の公有地についても実際されるよう検討すること。(財務大臣、厚生労働大臣)
児童扶養手当支給における扶養親族数の扱いの改善を求める要請
離婚によって単親世帯(特に母子家庭)となる場合、離婚前には扶養親族をもたなかった者が新たに扶養親族をもつようになることが少なくありません。
ところが、児童扶養手当には親の前年(または前々年)の所得とともに扶養親族の数を勘案した支給制限限度額が設けられていることから、結局、受給できる手当て額は扶養親族の数によって変動する仕組みになっています。
しかしその結果たとえば、離婚前まで共働き等で自分の所得があっても子どもを自分の扶養親族にしていなかった妻(または夫)が、離婚を機に実際に子どもを扶養することになっても、その扶養親族数は前年(前々年)の申告にもとづいてゼロとされるために支給制限がかかり、離婚直後の生活が厳しい時期に頼みの児童扶養手当が減額ないし不支給とされかねない事態も生じます。また、名古屋市がおこなっている「ひとり親家庭手当」も児童扶養手当の支給要件に準じるため、同様の制限がかかり、こうした家庭にとっては二重に不利な状況となります。
本来、児童扶養手当は、単親世帯の子育てと生活を支えることが目的であり、上のような制度上の矛盾は、同手当の趣旨と単親世帯の実態に照らし、早急に正されるべきであると考えます。
よって、以下のように要請します。
- 児童扶養手当の支給額は、実際の当年の扶養親族数を考慮した算定方法によるよう、制度や運用を改善してください。(厚生労働大臣)