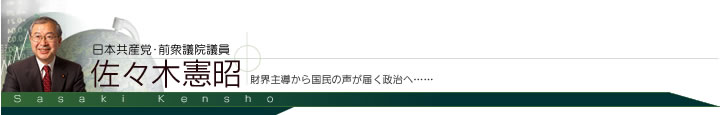奮戦記
【06.09.12】貯蓄ゼロ世帯が急増―その原因は、いったいどこに?
 今日の党議員団勉強会で、私は、次期政権の経済・財政政策について問題提起的な報告をおこないました。
今日の党議員団勉強会で、私は、次期政権の経済・財政政策について問題提起的な報告をおこないました。
そのさい、経済的な格差拡大の問題にふれたなかで、貧困化の指標のひとつとして貯蓄ゼロ世帯をとりあげました。
貯蓄ゼロの世帯は、約10年前の1995年には7.9%を占めるにすぎませんでしたが、2005年には23.8%を占めるまでに急増しているのです。――増えるテンポは、小泉内閣になってから特に高まっています。
 小泉内閣が誕生した2001年は16.7%でしたから、この間の増え方が急速なことがわかります。
小泉内閣が誕生した2001年は16.7%でしたから、この間の増え方が急速なことがわかります。
しかも、若者ほど貯蓄ゼロ世帯の比率が高く、20歳代で41%、30歳代で28.4%になっています。
若者のに2人に1人が非正規雇用となっており、不安定な雇用と収入が、その背景にあるように思います。
さらに重要なことは、「貯蓄残高が減少した理由」として、「定期的な収入が減ったので貯蓄を取り崩した」をあげている人が、増えていることです。
 たとえば、約10年前の1995年には36.6%を占めていました。ところが、2005年には、それが51.3%に増えているのです。
たとえば、約10年前の1995年には36.6%を占めていました。ところが、2005年には、それが51.3%に増えているのです。
それだけ、生活が苦しくなっている証拠です。
1世帯あたりの貯蓄残高をみると、1999年までは増え続けてきました。――それは、社会保障制度が十分ととのっていないため、老後や病気時などにそなえて貯蓄をするというのが一般的だったからでしょう。
 ところが、社会保障への不安がいっそう増しているにもかかわらず、貯蓄が取り崩されるのです。
ところが、社会保障への不安がいっそう増しているにもかかわらず、貯蓄が取り崩されるのです。
毎日の生活が格段に苦しくなり、将来のために蓄えていた貯蓄を、いまの生活のために取り崩さなければならなくなっているからでしょう。
その一方で、大企業が史上空前のもうけをあげ、多額の減税の恩恵を受け続けているのです。
こんな理不尽で不公平なことは、ないと思います。……“大企業に応分の負担を、庶民に負担の軽減を!”――これが、まっとうな政策ではありませんか?