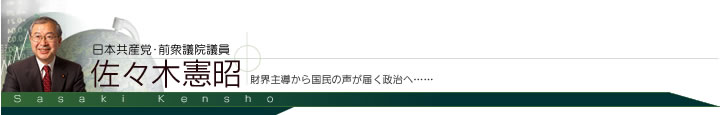奮戦記
【03.04.02】酒販関連法案について財金委員会で質問しました
 今日は、財務金融委員会で質問しました。
今日は、財務金融委員会で質問しました。
私はまず、まちの小さな酒屋さんが次々とつぶされていく「規制緩和」の問題についてききました。
90年代を通して「規制緩和」がすすめられてきましたが、特に98年の「規制緩和推進3カ年計画」でそれが決定的になりました。
2001年1月に「距離基準」が廃止され、いよいよ今年9月には、「人口基準」までも廃止されるのです。その酒屋さんへの影響は甚大です。
 1991年以降の10年間で、酒の小売業者は、一般小売店販売場数で、91年の131,267から2001年の146,436へ、15,169場(11.6%)増加しています。
1991年以降の10年間で、酒の小売業者は、一般小売店販売場数で、91年の131,267から2001年の146,436へ、15,169場(11.6%)増加しています。
国税庁の資料では、距離基準の廃止が始まった98年以降、2002年までの4年間で10781場も増えています。まさに出店ラッシュです。
酒販免許の付与は、この10年間で2万7396件もある一方で、取消・消滅が1万6754件も発生しています。消滅しているのは、零細な小売業者である町の酒屋さんです
 かつて、規制緩和が本格化する前は、販売場、数量とも、一般小売店が8割以上でした。それが、いまでは数量では5割を少し超えたところまで落ち込んでいます。
かつて、規制緩和が本格化する前は、販売場、数量とも、一般小売店が8割以上でした。それが、いまでは数量では5割を少し超えたところまで落ち込んでいます。
この統計の一般小売店のなかには、ディスカウントストアも含まれているため、個人商店であるまちの酒屋さんの割合は、これ以下です。
一方で、コンビニやスーパーでの酒の販売は、どんどん増えています。
あわせて、売り場数では8.6%から24.1%へ、販売量では12.3%からじつに30.5%にまで拡大しています。
これで明らかなように、規制緩和で急拡大しているのは、スーパーやコンビニでの酒販売なのです。
 全国小売酒販組合中央会が調べたところによると、人口基準の緩和がはじまる98年3月31日の閣議決定以降、今年2月末までの小売業者の窮状を示しています。それによると、転配業・倒産数が24,039件、失踪・行方不明者数が、2,547人、自殺者数が58人も出ています。
全国小売酒販組合中央会が調べたところによると、人口基準の緩和がはじまる98年3月31日の閣議決定以降、今年2月末までの小売業者の窮状を示しています。それによると、転配業・倒産数が24,039件、失踪・行方不明者数が、2,547人、自殺者数が58人も出ています。
財務大臣、このような痛ましい事態が生まれているのは、規制緩和が大きな要因になっていると思います。
 国税庁の「酒類販売等に関する懇談会」が昨年9月に出した報告書では、規制緩和の結果について、「規制緩和に伴い、新業態店が大幅に増加する一方で市場の変化が激しいため、一般酒販店は大幅に退出している」「競争に敗れ、あるいは競争にも参加できずに退出する一般酒販店が増大する等、小売業者の経営状況からみて急激・過度の参入による乱売等の競争の弊害が目立ってきている」と述べています。
国税庁の「酒類販売等に関する懇談会」が昨年9月に出した報告書では、規制緩和の結果について、「規制緩和に伴い、新業態店が大幅に増加する一方で市場の変化が激しいため、一般酒販店は大幅に退出している」「競争に敗れ、あるいは競争にも参加できずに退出する一般酒販店が増大する等、小売業者の経営状況からみて急激・過度の参入による乱売等の競争の弊害が目立ってきている」と述べています。
2月14日付の「日経」に「酒類販売に異業種続々」という記事が出ていました。
――「販売免許の自由化をにらんで、ピザチェーン、百円ショップ、レンタルビデオ店など異業種が酒類の販売に続々と参入している。酒を扱うことで、客の利便性を高め、集客効果の向上を狙う」。「マツモトキヨシなどのドラッグストアやホームセンター、ドンキホーテなどのディスカウントも続々と酒販免許の取得に動いている」との動きが紹介されています。

これまで酒販売と無縁だった企業が参入し、いっせいに酒を売るというのですから、ますます小売店への影響は大きい。
今回提案されている法案は、経営困難に陥っている既存の零細・中小業者に対する一定の対策としては賛成できます。
しかし、根本的には、規制緩和一辺倒路線の転換が、いまの零細業者の困難を解決するために必要です。
.