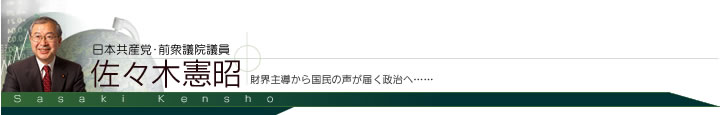奮戦記
【02.09.08】株下落は小泉内閣の経済政策への不信任
 東京株式市場の株価下落に歯止めがかかりません。バブル後の最安値です!
東京株式市場の株価下落に歯止めがかかりません。バブル後の最安値です!
<日経平均株価を伝える証券会社のボード)(写真=時事通信社)>――下落する日経平均株価を伝える証券会社のボード(6日午前10時55分、東京・日本橋)――
「株?関係ないね。持ってないから」――というわけにはいきません。なぜなら、株価は「経済の実態を映す鏡」だからです。株価の動きが景気の実態と先行きへの不安を反映していることは明らかだからです。
 小泉内閣が発足したとき、日経平均株価は1万4500円台だったのに、いまではなんと9000円を割り込むところまで落ち込んでしまったのです。
小泉内閣が発足したとき、日経平均株価は1万4500円台だったのに、いまではなんと9000円を割り込むところまで落ち込んでしまったのです。
塩川財務大臣は「上りもあれば下りもある」、福田官房長官は「株だから上がったり下がったりする」、などと相変わらず人ごとのようにトボケています。
ヘタなことを言うと株価に影響するからというよりも、まったく危機感がないということでしょう。
 ●小泉内閣で株価が3分の1落ちた
●小泉内閣で株価が3分の1落ちた
しかし小泉内閣のもとで、株価は一貫して下がりつづけ、3分の1が吹き飛んでしまいました。いまでは、一段と深い谷に落ち込んで先が見えないというのが実態です。
もはや「頼みの綱」であるアメリカがバブル崩壊に突入し、アメリカ向けの輸出増加で国内需要の冷え込みを補うなどというシナリオは完全に破たんしています。
東京電力、日本ハム、三井物産などそれぞれの業界を代表するトップ企業による不祥事の続発も、株価下落の大きな要因になっています。
 ●「構造改革」路線への不信任
●「構造改革」路線への不信任
小泉内閣は、不況が深刻化しているさなかに、「構造改革」を叫んで「不良債権の早期最終処理」を強行、倒産と失業を激増させました。
この政策が冷え込んだ家計を直撃し、日本経済を最悪の事態につき落としたのです。株の下落は、小泉経済政策への不信任です。
小泉首相は「痛みに耐えれば明日はよくなる」と言いました。しかし、実現したのは国民の「激痛」だけ。内需の自律回復どころか、消費を冷え込ませ経済の土台を破壊してきたのです。
このような政策を改めない限り、景気の回復は見込めません。
しかし小泉さんは、まったく懲(こ)りていません。
またまた、今年から来年にかけて3・2兆円もの医療・社会保障負担増で国民大収奪を強行しようとしているからです。
これが国民の先行きへの不安をさらに強めさせ、株価を一段と急落させているのは間違いありません。
 ●それでも愚策を繰り返すのか
●それでも愚策を繰り返すのか
政府・与党のなかでは「デフレ対策」の前倒しや補正予算の要求が強まっています。
しかし、その中心は不良債権処理の加速という倒産・失業増加策であり、失敗を重ねてきた公的資金の株式市場への投入であり、公共事業の積み増しなどです。
こんな対策しか出てこないこと自体、政権がますます袋小路に追い込まれ、かじ取り不能に陥っていることをしめしています。
いま、もとめられているのは小手先の対応ではありません。
ただちに国民大収奪を撤回し、くらしと家計を温める経済政策に抜本的に転換することが求められているのです。
<別添>「赤旗」主張もご覧下さい
.
.

.
. キャッ!!

.
<参考>
「赤旗」主張――株下落…経済こわす愚策への警鐘
--------------------------------------------------------
東京株式市場の下落傾向に歯止めがかかりません。
小泉内閣が発足して間もない昨年五月に一万四五〇〇円台をつけた日経平均株価は、九〇〇〇円を割り込むところまで落ち込んでいます。
福田官房長官は「株だから上がったり下がったりする」といいます。しかし、小泉内閣のもとで株価は一方的な値下がり傾向を示してきたのであり、それがいま一段と深い谷に落ち込んでいるのが実態です。
●「橋本不況」の二の舞い
株価は「経済の実態を映す鏡」といわれます。個々の投資家の思惑はさまざまであっても、一連の株価の動きが景気の実態と先行きへの不安を反映していることは明らかです。
小泉内閣は、国民が不況と失業に苦しんでいるときに、「構造改革」の名で「不良債権の早期最終処理」を強行し、倒産と失業を激増させてきました。この政策が冷え込んだ家計を直撃し日本経済を戦後最悪のマイナス成長にたたき落としました。
首相は「痛みに耐えれば明日はよくなる」と叫んできましたが、公約通りになったのは国民の「激痛」だけでした。景気回復の条件である国内需要の自律回復どころか、その土台を破壊してきたことが、ここ一年余の株価下落の背景にあります。
国民に「痛み」を強要する政策を改めない限り、景気の回復はあり得ません。にもかかわらず小泉内閣がやろうとしているのは、ことしから来年にかけて、過去最悪の三・二兆円もの社会保障負担増や庶民への増税という国民大収奪です。これが国民の先行きへの不安をさらに強めさせ、株価を一段と急落させているのは間違いありません。
小泉内閣の負担増政策が、一九九七年に橋本内閣が強行した消費税増税などによる大不況を想起させ、懸念を広げていることは明白です。
経済専門家からも警告の声が上がっています。「小泉改革は橋本改革の二の舞い」(高木勝明治大教授、『週刊エコノミスト』)。「(橋本内閣と)同じ失敗を繰り返すのが不思議なんですよ」(経済アナリストの森永卓郎氏、テレビ番組で)
重大なのは、日本経済の実態が、五年前と比べてはるかに深刻になっていることです。株価も、九六年末には二万円近い水準にあり、いまは格段に悪い条件です。
しかも、政権の頼みの綱のアメリカ経済が本格的なバブル崩壊に突入し、輸出増加で国内需要の冷え込みを補うシナリオは完全に破たんしています。
東京電力など財界を代表する大企業による不祥事の続発も、重しとなってのしかかっています。
このままでは「橋本不況」以上の経済破たんに真っ逆さまに転落する―。小泉内閣の経済政策こそ日本経済の最大の不安要因であり、その不安が市場にも反映しているのです。
●国民大収奪の撤回を
政府・与党では「デフレ対策」の前倒しや補正予算の要求が強まっています。「デフレ対策」といっても、中心は不良債権処理の加速という失業増加策にすぎません。ほかに取りざたされているのも、失敗を重ねてきた公的資金の株式市場への投入や、公共事業の積み増しです。こうしたやり方に道理も成算もないことははっきりしています。
こんな対策しか出てこないこと自体、政権がますます経済のかじ取り不能に追い込まれていることの証明にほかなりません。小手先の対応ではなく、国民大収奪を撤回し、くらしと家計を温める経済政策に抜本転換することが求められています。