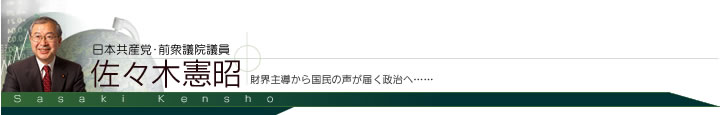奮戦記
【02.01.05】「構造改革批判」──2冊の本を読む
今日は、通常国会の論戦にそなえて、頭の体操をかねて「構造改革」を批判した本を2冊、読みました。
一冊は、山家悠紀夫『「構造改革」という幻想──経済危機からどう脱出するか』(岩波書店)、もう一冊は、小野善康『誤解だらけの構造改革』(日本経済新聞社)です。
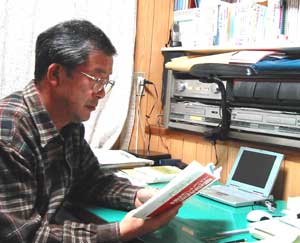
それぞれ、日本共産党とは立場が違う方々ですが、分析も主張点もじつに面白く参考になりました。
山家さんは、「構造改革なくして景気回復なし」という主張がいかに間違っているかを明らかにしています。90年代の日本経済の動向を分析して、長引く不況がバブル崩壊後の前期不況と橋本政権の「財政構造改革」後の後期不況が連続した結果だとのべています。とくに、後期の景気後退が、個人消費の落ち込みによってもたらされたものであるという指摘は興味深いものです。
さらに、いま、小泉政権が進めている「構造改革」が国民に無用の痛みを求めるものであると批判し、その危険性を指摘しています。「痛み」は、弱いところに集中すること、株価の動きに支配され経済がいっそう不安定になり格差が広がること、などです。
そのうえで、「別の選択肢」を提起しています。まず第一に「構造改革」政策の放棄もしくは「先送り」、第二に個人所得の拡大と雇用の拡大施策、年金など社会保障制度の充実、第三に規制の再構築、金融システムの再構築などです。
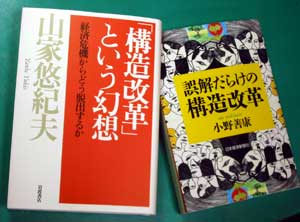
小野善康氏は、きわめて辛辣に「小泉構造改革」を批判しています。すぐれているのは雇用問題を重視していることです。その論点は、一部を除けば、われわれときわめて接近しています。
───「日本経済の潜在生産力が落ちているから不況なのではなく、需要が不足しているから不況なのだから、失業者を増やして需要を冷え込ませれば、さらに景気が悪くなるだけである」。「考えてみれば、ただでさえ需要に比べて生産能力が過剰な不況期に、これほど不況を深刻化させる政策はない。それなら、何もしない方がまだましであろう」
───不良債権処理で「おカネを貸した金融機関もろとも企業ごとつぶしてしまえということになると、責任者が罰を受けるだけではすまない。失業者を増やすことによって、本当の国民負担が起こってしまう。本当の解決法はこのようなツケ回しではなく、不良債権を優良債権にすることであり、そのためには貸出先に仕事を作って働かせればいいのである」。
なかなか鋭い! しかし、「公共事業」と「財政論」になると、納得しかねる部分が出てくるのは残念です。
たとえば、「経済の実質的な活動に対する効果という点では、社会保障の充実も、一般減税も、地域振興券も、緊縮財政も、すべて穴掘り穴埋め公共事業を大差がない」とか、「増税すれば、購買力を削いで景気を悪化させると信じられているが、……増税による財政支出増加とは、国民からおカネを取って同額を国民に返すだけである」ということが述べられています。
これは、経済実態から大きくかけ離れた議論ではないでしょうか。ゼネコン奉仕型の公共事業をいくら増やしても、雇用や最終消費の拡大にはつながらず、無駄と浪費、環境破壊をひろげてきたのです。
いま必要なのは、最終消費市場=家計消費をいかにして拡大するか、ここに政策の力点を置くことです。そのことに直結する年金、医療、介護、社会保障などの充実こそ、求められています。
.