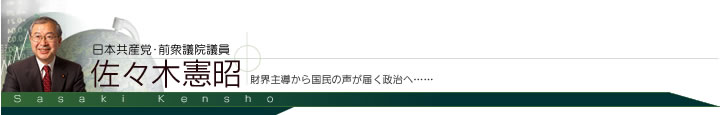�쳤�Ǥγ�ư
�쳤�Ǥγ�ư �� ���ܤؤ����������ӵ��ȡ����ΰ����������������ҳ������š����㳲�ԡ�ǯ�������ѡ�ϫƯ�Ԥθ��������θ�
��09.11.25�۰��θ��γ�����Ȥ����ä������������
��2009ǯ11��25���������ڷ����İ��ϡ����θ��γ�����Ȥ���������������Ԥ��ޤ�����������ϡ����ڸ��̾ʡ�����ܡ��ɺ�ô���ˡ����ӿ建�ʡ��Ķ��ʡ�����ϫƯ�ʤǤ���
�����������ˤϡ���¼�Τ֤����ް��θ����餷���Ķ��к��Ѱ�Ĺ�ˤ����Ϥ��ᡢ������ϯ���ް��θ���Ǥ�Ѱ��ˤ���ƣ�Ҥ�������컰�϶����Ѱ�Ĺ�ˤ������������İ��餬���á������ڵİ��Τۤ�����夵�Ȥ����ı��İ���Ʊ�ʤ��ޤ�����

���ڸ��̾ʤؤ�����ʸ
�߳ڥ�����߷ײ����ߤ��������
���������ʹ��ڸ�����äϣ�������ν�Ǥ�ǡ�����˰�¸����������������̸�ľ���ˤĤ��Ƹ��ڤ���������ޤ��Ϸײ��ʳ�������������Υ�����Ȥ�ľ���ͤ����ޤ������ޤ�����������ˤϡ���ʿ������ǯ�٤ˤ����������Ȥοʤ����ʤɤ˴ؤ����������ڸ�����äΥ����ȡפ�ȯɽ���졢������ǡ��߳ڥ��ࡢ��������Ϣ��Ƴ��ϩ��ޤࡢ��ڤӿ�������»ܤ��Ƥ��룴�����ȤˤĤ��Ƥϡ���������ǯ�ٰ���ˡ���(1)���������(2)����Ʒ�������(3)žή��������(4)���ι����γ��ʳ��˿���������ʤ����ȤȤ����������ʳ������뤳�ȤȤʤ빩���η�������Ϥ�����ʤɤϹԤ�ʤ����ȤȤ���פȤ��ơ������������餫�ˤ��ޤ�����
��̱���ޤ��������ʣ�������ǯ�������ȯ�ԡˤǤϡ��ָ��߷ײ���ޤ��Ϸ�����Υ���ˤĤ��Ƥϡ�����ä��٤���뤷��������֤��ߤ��ơ��ϰ輫���ν�̱�ȤȤ��ɬ������Ƹ�Ƥ����פ��������Ƥ��ޤ���
����ɤ�ϡ�����ޤǤ⼫���Ķ����ϰ�Ҳ���˲������߳ڥ���ײ�Ϥ���̵�̤ʥ�����Ȥ˰�Ӥ���ȿ�Ф��Ƥ��ޤ�������������Ω�줫���������ä����̱���ޤ�����Ǹ���������ȤΡ����ס���ɬ������Ƹ�Ƥ�פ��뤳�Ȥ����˼¹Ԥ˰ܤ����Ȥ���ꤦ��ΤǤ���
���߳ڥ�����Ȥϡ���̱�ޡ������������Τ�Ȥǣ�������ǯ��������������߳ڥ���η��ߤ˴ؤ�����ܷײ�סʰʲ������߳ڥ�����ܷײ�פȤ������ˤ����졢��������ǯ������Ρ��߳ڥ�����ߤ�ȼ��»�������ඨ���פ�Ĵ�������߳ڥ������Ʊ�դ˴ؤ��붨���פ�Ĵ�����Ԥ��ޤ�����
���߳�Į�䰦�θ��ν�̱�˽�ʬ��������ո���ʹ�����Ȥʤ��������˼�³����ʤ�礭������Τ���ײ�Ǥ���
�������������������ߡ��ϸ��к����ޤ������������ߡˤ��߳ڥ������Ū�ϡ�(1)����Ĵ�ᡢ(2)ή�������ʵ�ǽ�ΰݻ���(3)������(4)��ƻ�Ȥ���Ƥ��ޤ���
����ɤ�ϡ���������Ū�Τ�����⺬�ʤ����߳ڥ����ɬ�פΤʤ����Ȥ��ȹͤ��Ƥ��ޤ�������ͽ���Ϥ��߳�Į�Ƚ�̱�˼�꤫�����ΤĤ��ʤ��������դ��밦�θ���ǰ��η����ϰ���˲��ײ�Ǥ���
���߳ڥ���ι���Ĵ����̤ϡ���������ο�������Ĥν������ѤΣ���.����Ǥ��ꡢ���˸¤��Ƥ��ޤ������Ťʼ����Ķ����뤿��ˤ��̤���ˡ�����餷�ˤ������ɤʤ����ɶ����䡢��Ϣ³��ˤ��ͷ���ϡ��ФΥ���ȸ����뿹�����������Ϥ�Ŭ���ʴ����������������ϲ����ԻԲ��������ʤɡ�ή�����ΤǤμ���ײ�ˤ�ʬ��Ƥ����٤��Ǥ���Τˡ��ۤȤ�ɸ�Ƥ����ʤ��ޤޡ֥�����ˤ��꤭�פǿ�ʤ���Ƥ��ޤ���
��ή�������ʵ�ǽ�ΰݻ��˴ؤ��Ƥϡ��߳ڥ����ͭ���������̤Σ������������̡��Ϻ����̤ȹ���Ĵ�����̤���������ΡˤΣ���������ή�������ʵ�ǽ�ΰݻ����̤ȤʤäƤ��ꡢ����Ū�ˤߤƤ�ˤ�ư۾�ʥ���ײ�ȤʤäƤ��ޤ������⤽��������ߤ�������ο��ή�����Ǥ��뤳�Ȥϡ����������äƤ���ή�������ʵ�ǽ�������ΤǤ���
�������ڤӿ�ƻ�˴ؤ��Ƥ⡢��������ǯ�١ʣ�������ǯ����ˤ˴�������˭�������ѿ���Ȥdz��ݤ��졢���ߤϤ��褽����㎥��ۤ��붡��;�Ϥ�����ޤ����ޤ�������ο�μ����̤�����Ӥ�ЪΥ��������ʼ������ߤȤʤäƤ��ޤ���
������˿���ʤΤϡ������Ķ������ַϤˤ�������ƶ��Ǥ���
���߳ڥ������ͽ���Ϥˤϡ����פ��ȸ�����ư��ʪ�����Ǥ⣱�����濫�ꡢ���Τʤ����߳ڥ���η��ߤˤ�äơ�����©�Ϥξü������Ѥ�ȼ������©�Ķ���¿������©��Ŭ���ʤ��ʤ�פ��뤤�ϡ���©����ǧ���줿���Τ�¿�����ü������ư��ʪ�������濫�뤳�Ȥ�����ɤ⤬�Խ�ʬ���ȹͤ���Ķ��ƶ�ɾ����ˤ�����Ŧ����Ƥ��ޤ���
���Ȥ�櫓���ŷ����ǰʪ�ǡ������Τʤ��ǰ��θ���˭��黰�Ÿ��ε���ޤǤΰ��������Ѥ�ή���������ˤΤ���©���Ƥ���ͥ�������Ϳ����ƶ��Ͽ���Ǥ����Ķ��ƶ�ɾ����Ǥϡ�������ߤΤ�����©�Ǥ��ʤ��ʤ�ͥ�������ְܿ��פ���Ȥ��Ƥ��뤬����˭�����߳ڥ�������ȴĶ��ƶ�ɾ������Ф���Ķ���ðո��פǤ�ָ��ʳ��Ǥϥͥ������ΰܿ��˴ؤ����θ�����ʬ�������Ƥ���Ȥϸ����ʤ��פȻ�Ŧ���Ƥ���褦�˥ͥ������Ρְܿ��פϡ�����Ū�ˤ�̤��Ω�Ǥ��ꡢ�ºݤ˹��ڸ��̾ʤμ¸��ⲿ�٤⼺�Ԥ����ͥ������������貿����ˤ�錄�ä���©��³�����ݾ�Ϥɤ��ˤ⤢��ޤ���
����������ǯ�ˤϡ����θ�����ʪ¿���������裱����������ġʣãϣУ����ˤ����Ť���ޤ��������Ǥ⤳���ϰ�ˤ������ʤ����Ǵ����ɣ���Ǥ���ͥ�������˭��ˤ�����������©�Ϥ��˲������߳ڥ������ߤ��뤳�Ȥϡ���ʪ¿�����������˵չԤ��������ˤ��Ѥ��٤��٤Ǥ���
�����廊�ƻ����ѤؤδĶ��ƶ����ǰ����Ƥ��ޤ���
�����ܳ��γز��δĶ�����Ѱ���ϡ��߳ڥ���η��ߤϡ��֣�)���ˤ�ä����ѤδĶ��������ܼ�Ū�ʥ������奢��۴Ĥθ�����⤿�餹������)���ڤ�������Фα����������ؿ����ť���������ή�Ф��뤳�Ȥdz���¿�����٤�������������)����Ф��Ϻ���ȼ�äƳ��߿������®�������㡦������ü����������˴ؤ��ơ������Ѥؤαƶ���������ǰ����롣�פȻ�Ŧ���Ƥ��ޤ���
����ɬ�פʻ��Ȥ��ᡢ�ͥ������䥯�ޥ����ʤɤ���©���밦�Τ����Ȥ⤤���뤳�����������Ķ����ꡢ��ʪ��¿�������������뤿��ˡ��ʲ��������������ޤ���
- �߳ڥ�����ߤϡ�����ʿ�����̤��˴�Ť���������ή�������ʵ�ǽ�ΰݻ����̡פ�¿�����۾�ʷײ�ȤʤäƤ��ޤ����ޤ���������ߤ�ͽ���Ϥ���©������ŷ����ǰʪ�����Ǵ���������Υͥ������ϡ��鷺���������δ֤ǰ���Ū�������κ��ۤ�����Ȥθ����̤�ǤƤ��ޤ������ڸ��̾ʤ��ԤäƤ���ܿ��¸��Ǥϡ�����Ū�ʺ��ۤΤ���ͥ������Τ��٤Ƥ��ݸ�Ǥ���Ȥγξڤ������ޤ���
����ʪ¿��������������ij��Ź�Ȥ��Ƥ���Ǥ��̤���Ω��ˤ��������Τ褦�ʰ۾�ʷײ�Ǥ����߳ڥ�����ߤ���ߤ����˷��Ǥ��뤳�ȡ����ʤ��Ȥ��߳ڥ���ˤ�����룰��ǯ��ͽ���μ��ԡ���������ǯ��ͽ���ᡢ�����ϡ����ä�����뤷���ײ�θ�ľ�������˹Ԥ����ȡ�
- ˭���ϥե�ץ��ϡ���������ǯ����˴�������˭�������ѿ���Ȥ䣲������ǯ����˴����������٤�ȤäƤ��ʤ����ij�������ɤʤɤ�դޤ����夬;�äƤ�����֤�¨���ơ���������ľ����Ԥ����ȡ�
- ����ο��ή�����Ǥ�������ײ褷�Ƥ����ʤ��顢��ή�������ʵ�ǽ�ݻ��פΤ���˥����Ĥ���Ȥ�����̱���य�褦�ʻ��������뤳�ȡ�
- �����ȶ������Ƥ�������ˤ��߳ڥ�������ʤ�ή�����ΤǤμ���ײ�����餷�ˤ������ɤʤ����ɶ����䡢��Ϣ³��ˤ��ͷ���ϡ��ФΥ���ȸ����뿹�����������Ϥ�Ŭ���ʴ����������������ϲ����ԻԲ��������ʤɡˤ����ƺ��ꤷľ�����ȡ�
- �Ķ��ƶ�ɾ���ϡ������ѤؤδĶ��ƶ���ޤ��Τˤ��뤿��ˤ���ľ�����ȡ�
- ����ͽ���Ϥˤ��餹��̱�γ�����ϡ�����ǯ�ȥ�������ǡּؤ����������֤ˤʤäƤ��ꡢ�������������佻����������Ӥδ����ʤɤ⽽ʬ�ˤǤ�����»������äƤ��ޤ�����
�߳ڥ���η��ߤ�̵ͭ�˴ؤ�餺������ͽ���Ϥˤ��餹��̱�γ�����ؤ����衦�ĶȻٱ硢»�������Ԥ����ȡ��߳ڥ������ߤˤ����������Ū���Ť����äơ��߳�Į�γ������Τ���˻ٱ��Ԥ����ȡ����Τ���ˤ�ָ������Ȥ���ߤ�ȼ����̱������Ʒ����ϰ迶�����ʤ���ˡΧ�ʲ��Ρˡפ����ꤹ�뤳�ȡ�
���ڸ��̾ʤؤ�����ʸ
��������Ϣ��Ƴ��ϩ���߷ײ��¨����ߤ��������
��������������줷�������������Ф����̱Ū��Ƚ�ϡ����������Ρֹ�¤���ס�ϩ���Ȥ��碌�����ⴱ����Τ�ȤǸ��¤μ��פ�̵�뤷����ĥ�����������ȤΤ������Ǥ����������礭�������������̱���ޤ�������ޥ˥ե����Ȥǡ������Եޤθ������Ȥθ�ľ���פ����ޤ�����
�����¤ϡ����ͤƤ��ָ������Ȳ��ספ�ɬ��������졢��ǯ���̾�Ų�����ǻ�̱���Τ����Ť������ࡦƳ��ϩ����Υ���ݥ�����ǹֱ餵�줿�ʤ��ǡ���������Ϣ��Ƴ��ϩ�ײ����ϼ��ʷײ�פȤ��Ӥ�����Ƚ����ޤ����������̤�Ǥ���ޤ���
����������ο��ͬ���Ĺ�����������ͳ�����Ի��ѿ�ʿ�ƻ�ѿ塦�����ѿ�ˡ�����Ӱ۾�����β�������Ȥ��ơ����츩�Ȱ��θ��˰�����������Ƴ��ϩ�ײ�ϥ���˥����Ťͤ�̵�Ѥ��緿���ȤȤ��Ʒ�����ߤ���������ȱ�ư�����ͤƤ��³���������ޤ��ޤ��礭���ʤäƤ��ޤ���
����������ǯ��ʹߡ����ϰ�ˤ����Ƥ��Ի��ѿ�μ��פ����ڤ⤷���ϸ��������ˤ���ޤ�����̱��ȿ�Ф��ڤäƷ��ߤ��줿Ĺ����ϸ�����������ȯ���̤Τ��������������Ѥ���Ƥ��ʤ������������ߤ䥢�椬�㸺���إɥ��䥢���������ޤ�ʤɲ���Ķ������������ϸ������Υ����Ȥγ�����ű�������̱��ư�������äƤ��ޤ���
��Ĺ����ϸ������ˤĤŤ���ͬ�����ή�˷��ߤ��줿����������Ի��ѿ�ϴ��츩�����θ���̾�Ų��Ԥˤ�����ɬ�����Ϥ���ޤ��۾���������ˤ�����Ķ��ݻ��ˤĤ��Ƥ�ư��ʪ����©�Ķ������θ��̤ϵ��路�����դˡ������������ˤ�����ϲ�����Ŵ�ѥ��פ��̤äƤ���ͬ����ο���������뤳�Ȥˤ��Ĺ����ο�Ķ��ΰ�������Ŧ����Ƥ��ޤ���
��Ĺ����ϸ���������������ˤĤŤ�Ƴ��ϩ�η��ߤ���������������Τκ�����ô�Ȥʤꡢ��ƻ���Ȳ�פ���������̱����̱����������ô���Ȥʤ뤳�Ȥ����餫�Ǥ���
����¼������̾�Ų���Ĺ����������Ϣ��Ƴ��ϩ�����Ȥ����ű���ɽ�����줿���Ȥ������Ǥ��ꡢ���Ȥθ�ľ������ߤ����������ȿ�ǤǤ���������ʹ��̾�Ų���̱���оݤˤ����ʤä��ǿ�������Ĵ���ˤ��С���������Ϣ��Ƴ��ϩ�ˤĤ��ƣ�������ɬ�ספ���������ɬ�ספϤ鷺������Ǥ����ʡ������ף���������աˡ�
�����ڸ�����ä˽�Ǥ���줿���¤ϣ�����9������������Ϣ��Ƴ��ϩ���߳ڥ����դ��������ι�ľ��������ȤˤĤ��ơֺ�ǯ����˿������ʳ��ˤϤ��뤳�ȤȤʤ빩���η�������Ϥ�����ʤɤϹԤ�ʤ����ȤȤ���פȡְ�����פ�ɽ������ޤ�����
��Ƴ��ϩ�����Ȥ�Ĵ���ʳ��Ǥ��ꡢ�ײ����Ƥ��餤�äƤ�ط���̱�ΰ�ž���������Ʒ��Ȥ�������Ϥ���ޤ���
����äơ���������Ϣ��Ƴ��ϩ���߷ײ�ϡְ�����פˤȤɤ᤺�����äѤ���ߤ����褦���������ΤǤ���
����ܡ��ɺ�ô���ˡ����ӿ建�ʤؤ�����ʸ
����������ˤȤ�ʤ������ﳲ�εߺѤˤĤ��Ƥζ۵�����
����ǯ����������ܤä�����������ϳ��Ϥ��ﳲ��⤿�餷�ޤ��������Ȥ�櫓�컰���ϰ�ˤ����Ƥϡ����߱�ݤΥϥ�����Ϫ����ڡ����ʤɤβ̼¤��礭���ﳲ��⤿�餷�ޤ�����
�����ܤǤ�ͭ���Ρ��ÿ����������ϰ�Ǥ����컰�Ϥˤ����ơ��������ﳲ�ǡ����Ȥη�³����ǰ�������Ȥ⤦�ޤ�Ƥ��ꡢ�������ﳲ�����ȼ���Ψ�θ��塢¿�ͤ�����ʪ�������ˤĤ����礭���Ƿ�Ȥʤ��ΤǤ���
���Ĥ��Ƥϡ��ϰ�����Ȥ��뤿��ˡ��ʲ��Τ��Ȥ�۵ޤ��������ޤ���
- ���Ϸ�Ӻҳ��λ���Ƥ���������������ܡ�
- ���ȶ��Ѥ����٤������ﳲ�Τ�Ȥǡ����ȤΤ��Ƥʤ����ˤդ��路��������Ǥ����Τ˲������Ƥ���������
��»�������ϥ�����ű�����Ѥ϶��ѤǤϣ��������ߤޤǤ����Фޤ������Ȥ���ô�ʤ�ű����������褦�ˡ�����ʬ��Ķ�������ѤˤĤ��ƺ���Ū�ٱ�Ƥ��������������ӿ建�ʡ�
- ����������ˤ���ﳲ���ӵ��ȼ������Ф����ͻ�ٱ礬�����θ��ʤɤǹ֤����Ƥ��ޤ����������ﳲ�������Ȥ�Ω��ľ��������μ�����������ޤǤˤϻ��֤�������ޤ���
��������ͻ��ˤĤ��Ƥϡ����ʤ��Ȥ⣳ǯ�ο����֤�ͻ��ˤ��Ƥ����������ޤ��������ͻ��ˤĤ��Ƥ��ֺ�ͱͽ�����֤�֤��Ƥ���������
�������⡢��ž����ͻ���ǧ�����Ȥʤɤξ���Ĥ����ˡ��ﳲ����������ӵ��ȼԤ��ߤ��Ф��Ʋ������������ӿ建�ʡ�
- �����ﳲ�ˤ�äơ������Υϥ��������Ȼ��ߤ���ߤ��ʤ���Фʤ�ʤ���硢����Ū�ٱ��֤��Ʋ�������
���ޤ������Ȥ��ѶȤ��ʤ���Фʤ�ʤ��ʤä����Ȥ�����������Ǥθ������֤�֤��Ʋ������������ӿ建�ʡ�
�Ķ��ʤؤ�����ʸ
�߳ڥ������ͽ�������μ����Ķ�����ʪ¿�������������������
���߳ڥ�����Ȥϡ���̱�ޡ������������Τ�Ȥǣ�������ǯ��������������߳ڥ���η��ߤ˴ؤ�����ܷײ�סʰʲ������߳ڥ�����ܷײ�פȤ������ˤ����졢��������ǯ������ˡ����߳ڥ�����ߤ�ȼ��»�������ඨ���פ�Ĵ�������߳ڥ������Ʊ�դ˴ؤ��붨���פ�Ĵ�����Ԥ��ޤ�����
���߳�Į�䰦�θ��ν�̱�˽�ʬ��������ո���ʹ�����Ȥʤ��������˼�³����ʤ�礭������Τ���ײ�Ǥ���
�������������������ߡ��ϸ��к����ޤ������������ߡˤ��߳ڥ������Ū�ϡ�(1)����Ĵ�ᡢ(2)ή�������ʵ�ǽ�ΰݻ���(3)������(4)��ƻ�Ȥ���Ƥ��ޤ���
����ɤ�ϡ���������Ū�Τ�����⺬�ʤ����߳ڥ����ɬ�פΤʤ����Ȥ��ȹͤ��Ƥ��ޤ�������ͽ���Ϥ��߳�Į�Ƚ�̱�˼�꤫�����ΤĤ��ʤ��������դ��밦�θ���ǰ��η����ϰ���˲��ײ�Ǥ���
���߳ڥ���ι���Ĵ����̤ϡ���������ο�������Ĥν������ѤΣ���.����Ǥ��ꡢ���˸¤��Ƥ��ޤ������Ťʼ����Ķ����뤿��ˤ��̤���ˡ�����餷�ˤ������ɤʤ����ɶ����䡢��Ϣ³��ˤ��ͷ���ϡ��ФΥ���ȸ����뿹�����������Ϥ�Ŭ���ʴ����������������ϲ����ԻԲ��������ʤɡ�ή�����ΤǤμ���ײ�ˤ�ʬ��Ƥ����٤��Ǥ���Τˡ��ۤȤ�ɸ�Ƥ����ʤ��ޤޡ֥�����ˤ��꤭�פǿ�ʤ���Ƥ��ޤ���
��ή�������ʵ�ǽ�ΰݻ��˴ؤ��Ƥϡ��߳ڥ����ͭ���������̤Σ������������̡��Ϻ����̤ȹ���Ĵ�����̤���������ΡˤΣ���������ή�������ʵ�ǽ�ΰݻ����̤ȤʤäƤ��ꡢ����Ū�ˤߤƤ�ˤ�ư۾�ʥ���ײ�ȤʤäƤ��ޤ������⤽��������ߤ�������ο��ή�����Ǥ��뤳�Ȥϡ����������äƤ���ή�������ʵ�ǽ�������ΤǤ���
�������ڤӿ�ƻ�˴ؤ��Ƥ⡢��������ǯ�١ʣ�������ǯ����ˤ˴�������˭�������ѿ���Ȥdz��ݤ��졢���ߤϤ��褽����㎥��ۤ��붡��;�Ϥ�����ޤ����ޤ�������ο�μ����̤�����Ӥ�ЪΥ��������ʼ������ߤȤʤäƤ��ޤ���
������˿���ʤΤϡ������Ķ������ַϤˤ�������ƶ��Ǥ���
���߳ڥ������ͽ���Ϥˤϡ����פ��ȸ�����ư��ʪ�����Ǥ⣱�����濫�ꡢ���Τʤ����߳ڥ���η��ߤˤ�äơ�����©�Ϥξü������Ѥ�ȼ������©�Ķ���¿������©��Ŭ���ʤ��ʤ�פ��뤤�ϡ���©����ǧ���줿���Τ�¿�����ü������ư��ʪ�������濫�뤳�Ȥ�����ɤ⤬�Խ�ʬ���ȹͤ���Ķ��ƶ�ɾ����ˤ�����Ŧ����Ƥ��ޤ���
���Ȥ�櫓���ŷ����ǰʪ�ǡ������Τʤ��ǰ��θ���˭��黰�Ÿ��ε���ޤǤΰ��������Ѥ�ή���������ˤΤ���©���Ƥ���ͥ�������Ϳ����ƶ��Ͽ���Ǥ����Ķ��ƶ�ɾ����Ǥϡ�������ߤΤ�����©�Ǥ��ʤ��ʤ�ͥ�������ְܿ��פ���Ȥ��Ƥ��뤬����˭�����߳ڥ�������ȴĶ��ƶ�ɾ������Ф���Ķ���ðո��פǤ�ָ��ʳ��Ǥϥͥ������ΰܿ��˴ؤ����θ�����ʬ�������Ƥ���Ȥϸ����ʤ��פȻ�Ŧ���Ƥ���褦�˥ͥ������Ρְܿ��פϡ�����Ū�ˤ�̤��Ω�Ǥ��ꡢ�ºݤ˹��ڸ��̾ʤμ¸��ⲿ�٤⼺�Ԥ����ͥ������������貿����ˤ�錄�ä���©��³�����ݾ�Ϥɤ��ˤ⤢��ޤ���
����������ǯ�ˤϡ����θ�����ʪ¿���������裱����������ġʣãϣУ����ˤ����Ť���ޤ��������Ǥ⤳���ϰ�ˤ������ʤ����Ǵ����ɣ���Ǥ���ͥ�������˭��ˤ�����������©�Ϥ��˲������߳ڥ������ߤ��뤳�Ȥϡ���ʪ¿�����������˵չԤ��������ˤ��Ѥ��٤��٤Ǥ���
�����廊�ƻ����ѤؤδĶ��ƶ����ǰ����Ƥ��ޤ���
�����ܳ��γز��δĶ�����Ѱ���ϡ��߳ڥ���η��ߤϡ��֣�)���ˤ�ä����ѤδĶ��������ܼ�Ū�ʥ������奢��۴Ĥθ�����⤿�餹������)���ڤ�������Фα����������ؿ����ť���������ή�Ф��뤳�Ȥdz���¿�����٤�������������)����Ф��Ϻ���ȼ�äƳ��߿������®�������㡦������ü����������˴ؤ��ơ������Ѥؤαƶ���������ǰ����롣�פȻ�Ŧ���Ƥ��ޤ���
����ɬ�פʻ��Ȥ��ᡢ�ͥ������䥯�ޥ����ʤɤ���©���밦�Τ����Ȥ⤤���뤳�����������Ķ����ꡢ��ʪ��¿�������������뤿��ˡ��ʲ��������������ޤ���
- �����Ķ����ꡢ��ʪ��¿�������������뤿����߳ڥ�����߷ײ����ߤ��ᡢ��ʪ¿��������������ij��Ź�Ȥ�����Ǥ��̤������ȡ�
- ���ܳ��γز��δĶ�����Ѱ���Ŧ���Ƥ�����߳ڥ�����ߤ������Ѥ˵ڤܤ��ƶ���Ŭ����ɾ���Ǥ���Ķ��ƶ�ɾ���פ�Ϥ��ᡢ�߳ڥ���δĶ��ƶ�ɾ���Τ��ľ������뤳�ȡ��Ķ��ʤȤ��Ƥ��ȼ����߳ڥ�����ߤ������Ѥ�Ϳ����ƶ��ˤĤ���Ĵ�����뤳�ȡ�
- �߳ڥ�����߷ײ��Ϣ�δĶ���������ȼ�Ǥ���ˤ������Ķ��ʤȤ��Ƥ���ŷ����ǰʪ�����Ǵ���������Υͥ������䡢���Ǵ���������Υ��ޥ����ʤɵ��Ť�ư��ʪ�����ַϤ�μ¤˼���к���Ƥ������̱���äο����ʸ�Ƥ��Ĥ���������ޤ���������ޤȤ�뤳�ȡ�
����ϫƯ�ʤؤ�����ʸ
İ�о㤬�����ä��Ҥɤ⤿���ؤ���İ�����̵�����ʤɻٱ綯�����������
��̾�Ų��Ԥˤϡ���������İ�и���㤬���λҤɤ⤿�������ݸ�ԤȤȤ���̤��֤����Τ��ر�פȤ�����İ�Ļ��̱���ߤ�����ޤ���
�������Ǥϡ��㤬�����ä��Ҥɤ⤿����������ξ��̤���ǡ���(��İ��)��Ȥ������ȤФ�Ф����ä����Ȥ�ؤ�Ǥ��ޤ������ߡ��֤����Τ��ر�פ��̤�İ�о㤬�����ä������ͤλ�Ƹ�Τ������㤬���Լ�Ģ����äƤ��ʤ�İ�о㤬�����������ͤ���ȸ����Ƥ��ޤ������λҤɤ⤿���ϡ��ݰ��ʤɤ��̤äƤ����硢�ݰ����ȡ֤����Τ��ر�פ�����������Ť˻�ʧ��ʤ���Фʤ�ޤ���
����Ģ����äƤ��ʤ�����İ�о㤬�����ϡ���դ���ϡ�ȯã���ݾ㤹�뤿��ˤ���İ�郎ɬ�פ��ȸ����Ƥ��ޤ���
�����������������ڤʻ����λҤɤ⤿���ˤȤäơ���İ��Ϥ������ޤ������������ǥ��٥�β���ʹ�����ʤ��ȡ�����������ȯã��˾�᤺�������ȯã�˱ƶ�����ȸ����Ƥ��ޤ����첻�ϡ������礭�������Ҳ��ϲ�����������ΤǤ�������İ���Ĥ��ʤ���С��㤨�С��֤����Ĥ��פʤΤ��֤����Ĥ��פʤΤ�ʹ��ʬ�����ʤ����Ȥ⤢�ꡢ�֤����Ĥ��פȤ������դ�������Ƥ�������ˤϡ�ȯã�ʳ��λҤɤ⤿���ˤȤäơ���İ��ϡַ��١פǤ��äƤ�ɬ�פʤΤǤ��������������ߤ����٤Ǥϡ������ǥ��٥�ʾ�β���ʹ�����ʤ����Ǥʤ�����İ��ؤα���ϼ������ޤ���
���㤬���Լ�Ģ�Τʤ�����İ�о㤬���λҤɤ⤿���ϡ��Ҽ������ߤ���İ��ι������Ѥ������٤Ʋ�²�μ�����ô�ȤʤäƤ��ޤ�������˻Ҥɤ�ϡ�������Ĺ���뤿�ᡢ��Ĺ�ˤ��碌�����䡼�⡼��ɡ�ξ���ǣ����������������١ˤ⣱ǯ�ˣ��������㤤�ؤ��ʤ���Фʤ餺�����ηк�Ū��ô�����ѽŤ���Τ�����ޤ���
��̾�Ų��Ԥˤϡ����ͤλҤɤ⤵���ͤȤ����İ�о㤬����Ƚ�ꤵ�졢���ͤ�ξ������İ����䡼�⡼��ɤʤɤ����٤Ƽ�����ô�Ȥ����������⤢��ޤ������줵��ϡ����ͤλҤɤ⤵���֤����Τ��ر�פ��̤碌������ˣ��������ʤ�����İ�ص�פ�1�����̤碌����������������դǡ�Ư���˹Ԥ����Ȥ�Ǥ��ޤ���
���Ҥɤ�ϡ����������Ӳ�ä��ꡢ�Ϥͤ��ꡢ����줢�ä��ꤹ���ΤǤ������λ��ˡ���İ�郎����뤳�Ȥ⾯�ʤ�����ޤ����ˤ�夯Ǩ���Ȳ���Ƥ��ޤ��ޤ��������ơ���������Τ�ޤ����ۼ�����ô�Ǥ������������������������Ӥʤɤ��٤Ƥ�������ô�Ǥ�����Ư�����֤�ʤ��Τ���ô�����������Ƥ����פȤ���²�������ˤ������Ф���Ƥ��ޤ���
�����������֤��Ƥ����С����⤬�ʤ������λҤɤ⤿���ϡ���İ������롢�������������Ȥ������Ȥˤʤ�ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����
��̾�Ų��Ԥ�̾�Ų����ȼ����������ޤ���������¾���������ޤ�ư���δ�बɬ�פǡ��㤬���Լ�Ģ����Ԥ��оݤˤ��Ƥ���סʣ���������Ҥɤ��ľ�ǯ��Ĺ���ۡˤ��䤿�������Ǥ���
�����⤽��㤬���Լ�Ģ����Ԥ��оݤˤ���������Τϡ���Ǥ�����������٤��Ǥ���
���㤬���Լ�Ģ���ä��Ҥɤ⤿���⡢�֣�����ô�פȤʤäƤ��ޤ��������դ����ۤǤ��ꤺ�˼�����ô�����ʤ�ȯ�����Ƥ���Ȥ��������Ϥ��Ƥ��ޤ�����
��İ�о㤬�����ä��Ҥɤ⤿���ʽ��١����١����٤���鷺�ˤ��������ηкѻ���ˤ�ä�ɬ�פ���İ������뤳�Ȥ��ʤ��褦���ɤλҤ����������뤳�Ȥ��Ǥ���褦������ꤤ���ʲ��������������ޤ���
- ��������Τ������İ�郎ɬ�פʻҤɤ⤿���ϡ�İ�ϥ�٥뤬�����ǥ��٥�̤���ʤɤǾ㳲�Լ�Ģ���ʤ��Ƥ������٤Ȥ�����İ����䡼�⡼��ɤʤɤ�̵���ٵ����٤��äƤ������������ʤ��Ȥⲿ�餫�Τ���������ô��ڸ����Ƥ���������
- ���٤Ƥξ㳲���ä��Ҥɤ⤿����ɬ�פ��������̵�����ݾ㤷�Ƥ���������
- �㤬���ԡּ�Ω�ٱ��ˡ���ѻߤ����ֱ�����ô�פ��ᡢ�ϥ�ǥ���åפ�륵���ӥ���㤬���Ԥˤ�����������ϡ�̵���ˤ��Ƥ������������٤Ƥξ㤬���Ԥ��оݤˤ�������Ū�ʡ־㤬����ʡ��ˡ�פ�Ĥ��äƤ���������
���ڸ��̾ʤؤ�����ʸ
Υ���Ԥεサ������ݤ˸��������Ľ�����Ѥδ��ֱ�Ĺ�ο�������
�������ϡ�ʿ������ǯ����������ա�Υ���Ԥεサ������ݤ˸��������Ľ���γ��ѤˤĤ��ơסʹ����裸����ˤ�ȯ����������ˤ�꽻�������;���ʤ����줿�Ԥ��Ф��ơ����Ľ��𥹥ȥå�����Ѥ����к���֤��ޤ�����
������˴�Ť������θ��ϡ���������ǯ��������������ڤ�ˣ����ˤ錄�äƸ��Ľ���ʽ�����Ҥ�ޤ�ˤ���Ū�����Ѥˤ��������Ϥ������������Ϥǣ������ͤ�Υ���Ԥ˶��뤷�Ƥ��ޤ�����
����������Ԥϡ����ν������ܺ�����ߤȤ��Ʒ�̿�˽�����ư���ؤ�ƽ����Ǥ����Ԥ⾯�ʤ��餺���ޤ�Ƥ��ꡢͥ�줿�ܺ��Ȥ��Ƴ�ǧ�Ǥ��ޤ��������Ѿ����ϰ���˲�������ʤ�����ˡ�������¿��������ԤϺƽ����˻�äƤ��ޤ���������ǯ����������ߡ��������ͤ˰���³�����路�Ƥ��ꡢ���������Τˤ�����Ū�����Ѥ˷�����֤ϡ���§�Ȥ��ƣ�ǯ��Ķ���ʤ����֡פ������˷ޤ����ῦ�κ���˹�碌�ƺƤӽ�����¤ˤ����Ƥ��ޤ���
���ޤ������Τޤޤǿ�ܤ���ȡ����λܺ��˷��äƤ��뿦���ϡ����ȼԤ������뺤����ᤷ���Ż�����줳�ȤȤʤ�ޤ���
�����λܺ��ϡ�̾�Ų��Ԥ�Ϥᰦ�θ���ΤۤȤ�ɤμ����ΤǤ�»ܤ���Ƥ��ꡢƱ�������Ǻ��Ǥ������䤷�ޤ���
����äơ�Υ���Ԥεサ������ݤ˸��������Ľ���γ��ѤǤ�����֤��Ĺ����褦��������ޤ���
����ϫƯ�ʤؤ�����ʸ
�����������Ǥζ۵�����
����ǯ�Υ���ꥫȯ�ζ�ͻ�����Τ�ȡ����ܷкѤΰ����ȸ��������Ѿ����Ϻ������dz��Ǥ��Ƥ��餺�����ΤޤޤǤϺ�ǯ���ʾ�ˡ����佻��ä��ͤ��������դ����֤ȤʤäƤ��ޤ���
������������ΰ���ϫƯ�ɤ�ȯɽ�ˤ��ȡ�������ϫƯ�Ԥθۻߤ�ˤĤ��Ƥϡ���ǯ���������ǯ������ޤǤ˼»ܺѤޤ��ϼ»�ͽ���ϫƯ�ɤ��İ��Ǥ��Ƥ����Τǡ����������Ƚꣴ���������ͤ˵ڤ�Ǥ��ꡢ����ΰ��θ���ͭ�������Ψ�ϣ��������ܤȺ�����ΤޤޤǤ���
�������ʽ����褬�ߤĤ���ʤ��ޤ��ȵ��դ�����Ƥ��ޤä��͡��������ˤ��ޤ�Ƥ��ꡢ̾�Ų��Ԥ���¼�����Ǥϡ����ߤ⣱��������������ο��Ƚ���ä��ͤ��������̤�ˬ��Ƥ��ޤ���
�����������������ܤ�ȯɽ�����ֶ۵����к��פǤϡ����ȵ��դ��ڤ��ͤο����İ���������ǡ����մ��֤α�Ĺ�����֤�֤��뤳�ȤˤϤʤäƤ��ޤ���
�������ο���ʻ��֤��褹�뤳�Ȥϡ����ܤˤȤäƶ۵ޤβ���ȤʤäƤ��ޤ����ʲ��������������Ǥζ۵������ޤ���
- �絬�Ϥʡָۤ��ߤ�פ��������줿��������Ⱦǯ;���вᤷ�������ݸ��μ��ȵ��մ��֤��ڤ졢����������ͻ����ֺѤ��Ϥޤ�ޤ�����������¿����ϫƯ�ԤϤޤȤ�ʻŻ��˽����Ƥ��餺�����ΤޤޤǤ�ͻ����ֺѤɤ����������Ƥ������Ȥ����Ǥ��ʤ��ʤ�ޤ���
�����λ��֤ؤ��к��Ȥ��ơ����ȵ��դδ��ֱ�Ĺ��ͻ����ֺ�ͱͽ�ʤɤ����֤�ȤäƤ���������
- �ɸ�ϫƯ�Τ��������礭�ʼҲ�����ˤʤäƤ��ޤ��������ޤ��˰�ˡ���ɸ������Ȥ�����ޤ���
������Ĵ�����Ȥ���������������Ķ��ΰ�ˡ���ȯ�����������Ѥ����ϫƯ�Ԥο���ˤϿ�®���б����Ƥ���������Ʊ���ˡ�ϫƯ�Ԥο��𤬤ʤ��Ƥ⡢���Ū���ɸ�ϫƯ�θ����Ĵ��������ˡ���ɸ���ʤ�������λ�Ƴ��Ű�줷�Ƥ���������
- �ȥ西��ư�֤����ֽ��Ȱ��罸��Ƴ����Ƥ��ޤ����������ͭ�����Ѥ�ĤŤ��Ƥ����Ȥ��Ф����������Ѥ����䤹�褦�˻�Ƴ���Ƥ����������ޤ���ͭ�����Ѥ�ϫƯ�Ԥ��Զ��ˤĤ��Ƥϡ���Ȥ��Թ�Ǵ��֤����Ƥ���ΤǤ����顢����ϫƯ�Ԥ�Ʊ���ˤ���褦��Ƴ���Ƥ���������
- ���Ѿ����ΰ����ǡ����������������Ф뤳�Ȥǽ���⼺��ϫƯ�Ԥ������Ƥ��ޤ����ɸ�¼�Τ褦�ʥܥ��ƥ�����Ǥ����ΤǤʤ�����ȼ����Τ����Ϥ��ơ�����Ƚ�ϫ�λٱ����������뤳�Ȥ������Ƥ��ޤ���
�������ݸ����γ��ݡ������ΰ������������̤ʤɤ�����Ū�ˤǤ����ꡢ������֥�ȥåס�����������¿�����֤��Ƥ����������ޤ������Ū�����֤Ǥʤ������Ѿ��������������ޤǷ�³���Ƥ���������
- ϫƯ�����ζ���������������ˡ�����ϫƯ�ʤǤϿͰ��︺���������졢�ϥ���������ĺ��ʤɹ��������ӥ������ष�Ƥ��ޤ���
���������ᡢ�ष��ɬ�פʿͰ�����ԤʤäƤ����������ῦ�Ԥ��ص���Ϥ��뤿��ˡ�̾�Ų��̥ϥ�������ʤɡ��ĺ����줿�ϥ��������Ƴ����Ƥ���������
- ��ۤˤȤ�ʤ�������𤫤�������졢���ȤȤ�˽����ϫƯ�Ԥ������Ƥ��ޤ������δ֡�ͭ�������Ψ�ϣ�.�����٤����¤���̱�ִ�Ȥ˰�¸��������Ǥϸ��Ѿ����ι�ž�ϴ��ԤǤ��ޤ���
�����ĤƤμ����к����ȤΤ褦�ˡ���伫���Τ��Ѷ�Ū�ʸ����ϽФ˼���Ȥ�褦�ˤ��Ƥ������������κݡ�̤�и��λŻ��ˤ⽢����褦�ˡ������ؤλٱ��դ�����֤�ȤäƤ����������ޤ�������¥�ʽ�����ѻߤ�ľ���ʤɡ������Ԥؤν����������������Ƥ���������
����ϫƯ�ʤؤ�����ʸ
�ɸ��������°�ȿ��������Ƴ������³���ɸ����Ȥ�ϫ̳���Ƥ����ɸ��衢�ѥʥۡ��������Ҥ��Ф�����������ȡ������ɸ�ϫƯ�Ԥ�®�䤫�ʸۤ����촫���ȯư�����
�����������
��ϫƯ���ɸ�ˡ�ϡ��ɸ��������֤����¤�Ķ����ϫƯ���ɸ�����̳��������Ƥ���Ԥ��Ф���ˡ�裴������1��ε���ˤ���Ƴ��Ԥä��塢���μԤ��ʤ��������֤����¤�Ķ����ϫƯ���ɸ�����̳��������Ƥ�����ˤϡ������Ԥ��Ф����������Ԥ����Ȥ��Ǥ���Ȥ��Ƥ��ޤ����ޤ������ɸ�ϫƯ�Ԥ������ɸ���˸��Ѥ���Ƥ��뤳�Ȥ��˾���Ƥ�����ˤϡ������ɸ�����Ф����ɸ�ϫƯ�Ԥ�ۤ������褦���𤹤뤳�Ȥ��Ǥ���Ȥ���Ƥ��ޤ���
�����ε���ˤ����������ɸ������ҥ塼�ޥ�����������Ҥ��̤����ɸ���ѥʥۡ��������Ҥ��ɸ����Ȥ���Ƥ���ϫƯ�Ԥ��ݸ��¸����뤿�ᡢ�������𡢸ۤ����촫���ȯư����ޤ���
���ʲ��ܺ٤ˤĤ����������ޤ���
�������·в����������
��������ϣ���ǯ���������ꡢ�ɸ����ҥ塼�ޥ�����������Ҥ���Ͽ���ɸ�ϫƯ�ԤȤ��ơ��ѥʥۡ��������������Ķ���ȯ�ټҷ������˽��ȤϤ��ޤ�����
���������Σ���ˤ�Ʊ�Ҥλ������ܤ����ꡢ���⥤��ȥ�ͥåȤλ��ѵڤӹ���ô���ԤΥ��ݡ��Ȥʤɡְ��̻�̳��̳�Ǥ������������ޤ�����
��Ʊǯ�������ҥ塼�ޥ�����������ҤαĶ�ô���Ԥ���̳���Ƴ�ǧ�����Ȥε��������줿���ᡢ���¤��������Ȥ����֤���Ǥϡ������̳�Ȥ��ơ��̤�ʤ��פȤ�̿��ǡ���ľ�������ޤ������ʸ塢������Ϸ����ˤ���֣����̳�������פȼºݤζ�̳���Ƥ˰��´������������Ƥγ�ǧ���ѹ����֤�����Τμ���������ޤ���Ǥ�����
��������ϣ���ǯ������ܤˡ��������Ǥθۤ��ߤ�����Τ���ޤ�������Ǽ���Ǥ��ʤ����ᡢƱ������˰���ϫƯ�ɼ���Ĵ���������˿��𤷤ޤ��������η�̡�ϫƯ�ɤ���ϡ���̳�μ��֤������̳�Ȥϸ���������ͳ����̳�Ǥ��ä����Ȥ���ǧ���졢���Ǥ˸�§��ǯ�δ������¤�Ķ���Ƥ������ᡢ������Ƴ�ڤ�ľ�ܸ��Ѥο侩��Ƴ��Ԥ�����������ޤ�����
������������������˰���ϫƯ�ɤ����Ƴ��������ҥ塼�ޥ�����������Ҥ��֥ѥʥۡ�����ä���ä���̡ף�������������Ƥϡ�Ʊ���ꡦƱ���̳���ɸ����ȱ�Ĺ�Ǥ�����
������ϡ��������¤�Ķ���Ƥ����ɸ���̳�˰���³���ɸ�����̳��������뤳�ȤϽ���ʤ��Ȥ������Ǥ��������ۡ�����ϫƯ�ʤθ����ȿ�����ΤǤ���������������Ƴ�ˤ�ؤ�餺�ɸ����Ȥ���³���Ƥ��뤳�Ȥϡ�ˡ������ˤ���������ۤ����촫�𤬹Ԥ���٤���ΤǤ������Τ��������Ϥ������Ф���ϫƯ���ɸ�ˡ��ȿ�Ǥ��뤳�Ȥ��Ŧ��������δ�˾�ϥѥʥۡ��������ҤǤδ��֤����Τʤ�ľ�ܸ��ѤǤ���ݤ������ޤ�����
��������Ф��ƥѥʥۡ���ȥҥ塼�ޥ������ϡ��ִ������¤ϣ�ǯ�ǡ���ǯ��Ķ���Ƥ��Ƥ��ɤ��פ��������Ƥ��ޤ������κ���Ȥ��ơ�����ǯ����������ѥʥۡ���ˤ�룱ǯ�δ������������Ǥ��ä����Ȥϻ��¤Ǥ��ꡢ�������Ȥ��룰��ǯ���������Σ���ǯ�������Ʊ���̳�Ƥ����ͤ�ޤᡢ���������ޤ��Ȥ����Ƥ������Ȥ�ǧ��뤬���ְִ㤤���Ȥϻפ�ʤ��ä��ס��������̳���ȻפäƤ����פ��ᡢ����ϫƯ�ɤ�����̵ڤ��������α�Ĺ��³����Ԥ��褦��Ƴ���줿���Ȥ��Ƥ��ޤ��������Ƹ��ߡ�������ؤϣ�������ǯ��������������Ȥ��������ʸ��ѷ�������졢���裰��ǯ�������Ƿ���λ��ͽ��ʤ��顢�ֽ�����ư��ͱͽ�Τ���ף�����ֱ�Ĺ�������������äƸۤ��ߤ᤹��ȼ�ĥ���Ƥ��ޤ���
�����Τ褦�ˡ�ϫƯ�Ԥο���ˤ���ˡ���֤�ǧ����ʤ��顢��Ȥ���ˡ��Ģ�ä��ˤǤ�����ۤޤǤǤ���ʤɤȤ������Ȥ�����С����Τ���ο������٤��狼��ޤ���
���⤷����ϫƯ�ɤ��������̤ä��������Ĺ�Ǥ���Ȥλ�Ƴ��ԤäƤ����Ȥ���н��������Ǥ�����§��ǯ�δ������±�Ĺ�ϡ���ǯ��ޤ������ޤǤ�Ŭ�ڤʱ�Ĺ��³����Ԥ����Ȥˤ����磳ǯ�ޤǿ��Ф����Ȥ���ǽ�ʤΤǤ��äơ�Ŭ�ڤʼ�³�����ʤ���ʤ���С�1ǯ�δ������¤Ϥ��λ����dz��ꤹ��Τ������Ǥ������θ�§�ϡ��ɸ������Ұ������ؤȤ��ʤ��Ȥ���ˡ�μ�ݤ�ô�ݤ��뺬����ʬ�Ǥ���Ϥ��Ǥ���
���ѥʥۡ��ࡢ�ҥ塼�ޥ�����ξ�Ҥ������ꡢ��̳�μ��֤������̳�Ǥʤ����Ȥ�ǧ�����Ƥ������Ȥϡ��������ܤǤ������䡢��̳���Ƥβ��������٤�������餫�Ǥ���ˡ��ȿ�ˤ��������°�ȿ��ǧ�ꤵ�줿�ʾ塢����ʸ���ɸ�ϫƯ�Ԥ�ۤ������ΤǤ����������ľ�ܸ��ѤȤ��٤��Ǥ��������ɸ����ꡢ�ΰդ˴������¤�������������տ�Ū�˵��������Ȥ��Ф������������ʤ�ˡ��������Ǥ����ʤ��¤ꡢ���Τ褦��æˡ����ˡ�Ϻ��䤵��ޤ������ǡ��ʲ������ˤĤ����������ޤ���
- ��Ȥ���ˡ��ư�ˤ���ﳲ�ˤ��äƤ���ϫƯ�Ԥ��ݸ��¸����뤿��ˡ�ϫƯ���ɸ�ˡ�ˤ��äƤ������˸���ϫƯ���̾�ˤ���������𡢸ۤ����촫���ȯư�����ֶ�̳�谷���Ρפˤ���褦�ˡ����֤����Τʤ����Ѥˤʤ�褦���𤹤뤳�ȡ�
- ����˽���ʤ���硢ˡ�ε���ˤΤäȤ���̾�ڤӽ���ϡ����Ƚ�̾�ڤӽ�����¤Ӥ˻�Ƴ�����������𡢵ڤӸ�ɽ�ηаޤ��餫�ˤ��뤳�ȡ�
- ���֤����Τ����ɸ���̳�δ������¤ϸ�§1ǯ�Ǥ��뤳�Ȥλ�ƳŰ�졢�¤Ӥ������ϲ����̤äƱ�Ĺ�Ǥ��ʤ��Ȥ������ȤˤĤ��Ƴ�ǧ����ޤ���
��ȷ�������������δ��ܤȤʤ�ֻ���ϢΩ��աפˤ����ơ�����ϫƯ���ɸ�ˡ��ϫƯ���ݸ�ˡ�ؤȸ�ľ���Ȥ��Ƥ��ޤ��������ΤޤޤǤϴ丵�����ˡ�������Ԥ�;͵�Τʤ��ޤޣ��������˲�ۤ���Ƥ��ޤ��ޤ����������ä����ܤˤ����Ƥϡ������ɸ�ˡ�Τ�ȤǤ��ǽ�ʸ¤�μ��Ԥ�������Ȥ˸�����Ǥ������٤�����ޤ��б����Ƥ����������Ȥ���ޤ���
���ڸ��̾ʤؤ�����ʸ
ϳ�夷����������ɤβ��������������Τ˽Ť�������ô���Ĥ��뤳�Ȥʤ�������뤿�ᡢΥ�翶��ˡ�β�����������
������¿Į��Ⱦ�����������ֲ���������ѿ������ݥꥨ��������γ�������ɤ���»�������������������ȥ��ϳ�夬�����Ƥ��뤳�Ȥ���ǯ�����Ĵ�������餫�ˤʤ�ޤ���������ι�����ϣ��ȥ������ߤǤ��ꡢ�������������ߤ��ﳲ���ǤƤ��ޤ���
�����ֲ���ؤγ�������ɤϡ�����¿Į�պ���Ӻ꤫�����ֲ���������ͤΣ���������ȥ�����̤ˣ��ܡ���������ǯ�����ߤ���ޤ���������ǯ��вᤷ�Ƥ��ޤ���
�������ϳ���к��Ȥ��ơ�����ɤ�ݻ��������Ƥ�������¿Į�ϡ�ϳ����ʬ��ޤࣱ��������ȥ���ʬ�μ�괹����Ƥ���Ƥ��ޤ������������Ѥ����ߤ�����Ȥ����Ƥ��ޤ���
������¿Į�Ȥ��Ƥϡ��������Ѥ�Ⱦʬ�ĤǤޤ��ʤ����Ĥ�Ⱦʬ��쿧Į����Ⱦ���뤳�Ȥ��Ť������ȸ�Ƥ���Ƥ��ޤ�����¿�ۤ����ѤФ��뤳�Ȥϡ�Į�����礭�ʱƶ���Ϳ�������������Τ����Ǥ���Į̱�ؤ�ʡ��Υ����ӥ��ˤ�ƶ����Ǥ��ͤޤ���
��Υ�翶��ˡ�ʣ�������ǯ�����������ˤ����ꤵ��ư��裵��ǯ���вᤷ�Ƥ��ޤ������δ֡�Υ��ˤ����������⤹�����졢�Ƽ���ߤ�Ϸ�ಽ�������ߤι�����ɬ�פȤʤäƤ��Ƥ��ޤ�����������Υ�翶��ˡ�ϻ��ߤΰݻ�������Ϸ����ߤι����κ���Ū�ٱ�ˤĤ��ƹ�θ����Ƥ��ޤ���
��Υ����������������Τϡ������ƺ���Ū�˺���Ǥ��ꡢϷ����ߤι�����¿��ʺ�����ô�����������Τˤ����뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
��¿��ʺ�����ô������¿Į�˲����Ĥ��뤳�Ȥʤ����պ�����ֲ��糤�������ϳ��β��������������褦�ˡ��ʲ��Τ��Ȥ��������ޤ���
- Υ�翶��ˡ�ˡ����ߤΰݻ������ڤ�Ϸ����ߤι����ؤκ���Ū�ٱ��ä���褦�˲��ꤷ�Ƥ���������
����ϫƯ�ʤؤ�����ʸ
ϳ�夷���պ�����ֲ��糤������ɤβ����ˤĤ��ơ�Ϸ��ɤι������ȤȤ���ǧ�ᡢ�����ٱ���������
������¿Į��Ⱦ�����������ֲ���������ѿ������ݥꥨ��������γ�������ɤ���»�������������������ȥ��ϳ�夬�����Ƥ��뤳�Ȥ���ǯ�����Ĵ�������餫�ˤʤ�ޤ���������ι�����ϣ��ȥ������ߤǤ��ꡢ�������������ߤ��ﳲ���ǤƤ��ޤ���
�����ֲ���ؤγ�������ɤϡ�����¿Į�պ���Ӻ꤫�����ֲ���������ͤΣ���������ȥ�����̤ˣ��ܡ���������ǯ�����ߤ���ޤ���������ǯ��вᤷ�Ƥ��ޤ���
�������ϳ���к��Ȥ��ơ�����ɤ�ݻ��������Ƥ�������¿Į�ϡ�ϳ����ʬ��ޤࣱ��������ȥ���ʬ�μ�괹����Ƥ���Ƥ��ޤ������������Ѥ����ߤ�����Ȥ����Ƥ��ޤ���
������¿Į�Ȥ��Ƥϡ��������Ѥ�Ⱦʬ�ĤǤޤ��ʤ����Ĥ�Ⱦʬ��쿧Į����Ⱦ���뤳�Ȥ��Ť������ȸ�Ƥ���Ƥ��ޤ�����¿�ۤ����ѤФ��뤳�Ȥϡ�Į�����礭�ʱƶ���Ϳ�������������Τ����Ǥ���Į̱�ؤ�ʡ��Υ����ӥ��ˤ�ƶ����Ǥ��ͤޤ���
��¿��ʺ�����ô������¿Į�˲����Ĥ��뤳�Ȥʤ����պ�����ֲ��糤�������ϳ��β��������������褦�ˡ��ʲ��Τ��Ȥ��������ޤ���
- ���ֲ���ؤ�����ɤϡ����Ǥˣ���ǯ��вᤷ�Ƥ��ꡢ�ֿ�ƻˡ�סֿ�ƻ�帻��ȯ�����������������������ˡפ�Ϸ��ɤι������ȤȤ���ǧ�ᡢ����Ū�ٱ�Ƥ���������