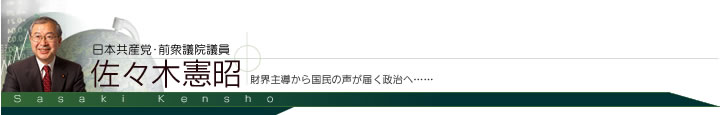奮戦記
【06.04.06】憲法改悪のための国民投票法案に反対する請願デモ

昼の12時半から、憲法改悪のための国民投票法案に反対する昼休み請願デモを激励しました。5・3憲法集会実行委員会が主催したものです。

衆議院の議員面会所に参加したのは、社民党と日本共産党の議員です。日本共産党からは、志位和夫委員長、石井郁子副委員長、穀田恵二国対委員長、吉井英勝議員、赤嶺政賢議員、塩川鉄也議員、笠井亮議員、そして私も参加しました。

今日から医療改悪法案の審議が始まりました
 今日、衆議院本会議で医療改悪法案の審議がおこなわれました。日本共産党を代表して質問したのは、高橋千鶴子衆議院議員です。以下、質問の内容をご紹介します。
今日、衆議院本会議で医療改悪法案の審議がおこなわれました。日本共産党を代表して質問したのは、高橋千鶴子衆議院議員です。以下、質問の内容をご紹介します。
私は、日本共産党を代表して、「健康保険法等の一部改正案」及び「医療法等の一部改正案」について、総理及び厚生労働大臣に質問します。
小泉内閣の5年間、年金や医療などの連続改悪で負担増と給付減が繰り返えされてきました。その上、4月から障害者自立支援法や介護保険の負担増が始まります。この社会保障の切り捨てが、老後や病気などへの国民の力を削り取り、経済格差を押し広げてきました。
今日、長時間労働はいっそう深刻となり、非正規雇用が3割にも達し、生活保護も100万世帯を超えています。その中で、国民の間には、深刻な健康被害が広がり、社会保障に対する、強い不安や不満が広がっています。本法案による負担のさらなる押し付けが、、この格差をいっそう広げることは明らかです。
 とりわけ、国民皆保険の土台である国民健康保険の事態は深刻です。
とりわけ、国民皆保険の土台である国民健康保険の事態は深刻です。
保険料の滞納が470万世帯に達し、保険証の取り上げはこの5年間で3・3倍に拡大しています。
正規の保険証がないために病院にも行けず、そのためにいのちを落とすなど悲惨な事件も報じられています。
国民医療の現実が、ここに象徴されていると考えます。この深刻な事態について、どう認識するか、見解をお聞きします。
本法案の特徴の一つは、高齢者などへの情け容赦ない負担増と医療の切捨てにあります。もう一つは、医療給付費の削減を「医療費適正化」計画に定めて強行し、混合診療など保険の効かない医療を拡大しようとするであります。
第一に、患者負担の拡大について聞きます。
本法案によれば、今年10月から、70歳以上の「現役並み所得者」の窓口負担は2割から3割になります。療養病床に入院する70歳以上の食費・居住費も保険の適用がはずされ、自己負担となります。この負担増は、2008年4月からは65歳以上に対象が拡大され、1ヶ月の入院費は13万円をこえてしまいます。
さらに、医療費が高額になったときの「高額療養費制度」も限度額が引き上げられます。人工透析患者に対しては、一定所得以上の負担を、月額1万円から2万円に増やそうというものです。
「医療費の削減」を理由に、高齢者や重い病気に苦しむ患者に負担を強いることは、いっそうおおきな苦痛を押しつけると思いませんか。
 2008年4月から導入される「高齢者医療制度」は、現在家族に扶養され保険料がかからない240万人の高齢者も含めて、75歳以上のすべてを対象にして、年間平均で7万4000円の保険料を徴収するというものです。
2008年4月から導入される「高齢者医療制度」は、現在家族に扶養され保険料がかからない240万人の高齢者も含めて、75歳以上のすべてを対象にして、年間平均で7万4000円の保険料を徴収するというものです。
介護保険料と合計すると月額1万円を超える額が年金から「天引き」されます。
有病率が高く、病院に通う機会の多いお年よりに対して、いわば狙い撃ち的に負担の拡大を押し付けることは許せません。医療機関への敷居を高くすれば、国民の健康を破壊するだけではないでしょうか。
つぎに、「医療費適正化計画」や療養病床削減などについてです。
経済財政諮問会議は、GDPの伸び率と高齢化を加味した「基準」で医療費を管理し、医療給付費の総額抑制を求めました。本法案では、「医療費適正化計画」を策定して「目安指標」を定めるとしています。ともに医療費を抑制しようとするものですが、この「目安」とは、いったいどの様な内容を持つものですか。具体的数値などを示して「適正化計画」に盛り込むことになるのですか。
都道府県の「医療費適正化計画」では、国の「基本方針」にそって、生活習慣病や在院日数などの数値目標を定め、この目標が達成できなかったり、全国平均を下回った場合には、都道府県の責任を求めるという内容になっています。
生活習慣病を減少するために、国民の健康の悪化の原因を取り除き、健康診断や保健指導を引き上げ、疾病の早期発見・早期治療体制を整備するなどは、本来、国の責任で行われるべき施策ではありませんか。答弁を求めるものです。
平均在院日数の削減については、全国平均の在院日数ともっとも短い県との差を半分に縮小するという目標を立てます。国は、この目標達成度を評価して、診療報酬の「特例」を都道府県が設けることができるとしています。この「特例」が、患者を病院から追い出し、医療機関に病床転換を強要するなど、事実上、懲罰的な設定とはなりませんか。
 政府は「医療の必要度が低い」といって、現在38万床ある療養病床を、今後6年間でその6割、23万床を削減するとしています。しかしそれでは、長期入院患者に必要な医療的管理や容態の急変に適切に対応する病床の確保ができなくなりはしませんか。
政府は「医療の必要度が低い」といって、現在38万床ある療養病床を、今後6年間でその6割、23万床を削減するとしています。しかしそれでは、長期入院患者に必要な医療的管理や容態の急変に適切に対応する病床の確保ができなくなりはしませんか。
「施設から在宅へ」が国の方針です。ところが在宅医療の体制や地域での介護の体制はどうでしょうか。たとえば、特別養護老人ホームが足りなくて、待機者が38万人を超えるなど、地域の「受け皿」はまったく不足しています。病床が削減されれば、入院患者の行き先がなくなります。これは、患者の追い出しそのものではありませんか。お答えください。
そもそも、日本の医療費水準は国際的にみて決して高くはありません。一人当たりの医療費はOECD加盟国中9番目。総医療費をGDP比較で見ると7.9%で17番目です。医療費の削減どころか、経済力に見合った医療の充実こそ、果たすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
最後に、保険の効かない医療を拡大することについてです。
日本経団連は、医療の「給付費の増加を抑えるため、保険外サービスと保険サービスの併用を進めるべきである」と主張し、大企業の保険料負担を軽減したいという強い要求を露骨にしています。
 昨年の厚生労働省の「医療制度改革試案」には、外来受診1回当たり500円〜1000円までを保険の対象からはずすという「保険免責制度」が盛り込まれました。
昨年の厚生労働省の「医療制度改革試案」には、外来受診1回当たり500円〜1000円までを保険の対象からはずすという「保険免責制度」が盛り込まれました。
リハビリなど、定期的に通院が必要な患者にとっては負担が大きくなり、風邪や腹痛ぐらいでは病院にいくのを我慢することになるのは避けられないと思います。
本改正案には入りませんでしたが、政府文書に書き入れたこと自体がきわめて重大です。今後、「保険免責制度」の導入はすべきでないと考えますが、明確な答弁を求めます。
現在は、差額ベット代などの徴収を例外的に認めています。この「特定療養費制度」を、保険に適用するための評価を行う療養費と将来の保険の適用を前提とせず、患者が選択できる療養費とに再編しますが、これまで例外的であった差額ベッド代など以外にも「高度医療技術」や「生活療養」などの名目で、保険を適用しない分野を拡大する懸念があります。
そうなれば、新しい医療技術や新薬の利用、手厚い治療などは、お金のある人だけが受けられ、そうでない人は十分な治療が受けられないという「治療の格差」をつくり出すことになります。「所得の格差」が「命の格差」につながるような社会は、あってはならないと考えますが、いかがでしょうか。
憲法25条の精神にてらして、医療での国の責任と負担を大幅に拡充し、すべての人が、安心してかかれる医療制度を築くべきです。
本改正案は、この道を大きく踏みはずすものであり、撤回を強く求めて、私の、質問を終わります。