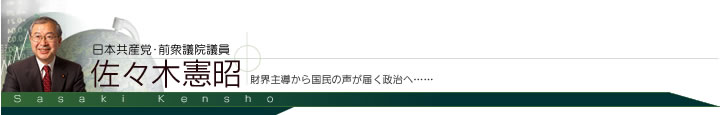奮戦記
【06.02.27】自民党の公約違反、財務省の天下りで財金委・質問
 今日は財務金融委員会が開かれました。
今日は財務金融委員会が開かれました。
私は、所得税の「定率減税」全廃法案と、国税庁による国税OB税理士への顧問先斡旋・天下り問題について、谷垣財務大臣に質問しました。
提案されている法案には、個人所得課税について「定率減税の廃止」が盛り込まれています。
これは、今年1月から半分実施されたのに続いて、来年1月から残りすべてを廃止するというものです。
 自営業者やサラリ−マンなども含むすべての所得税納税者が、増税の対象になります。
自営業者やサラリ−マンなども含むすべての所得税納税者が、増税の対象になります。
そのうち、サラリーマンは86.9%を占めています。中心は、サラリーマン世帯です。
昨年6月21日に政府税制調査会が出した「個人所得課税に関する論点整理」という報告があります。
まず最初に「個人所得課税の抜本的見直し」として、「平成18年度においては、定率減税を廃止する」と書いています。そのうえで、給与所得控除など各種控除を見直すことが検討されています。
 今回の「定率減税」廃止法案は、この政府税調の考え方にそって出されたものです。
今回の「定率減税」廃止法案は、この政府税調の考え方にそって出されたものです。
しかし、そういうことをしないというのが、自民党の政策だったのではないでしょうか。
昨年夏の総選挙で、自民党は「選挙公約」(マニフェスト)で「『サラリーマン増税』を行うとの政府税調の考え方はとらない」と述べていました。
しかも自民党の武部幹事長は、こう言っていました。
――「政府税調のサラリーマン増税ありきを自民党は『許さない!』 武部幹事長 政府税調を強く批判」。
――「6月21日に政府の税制調査会が発表した『論点整理』について、武部幹事長は『サラリーマン増税なんて安易に許さない』と、政府税調を強く批判しました」。
 ――「武部幹事長は『これはあくまで論点整理であって、党税調がしっかり対応します』とし、自民党の税制調査会で税制改革の議論を行い、政府税調の論点整理どおりの『サラリーマン増税ありき』を否定しました」。こう書いています。
――「武部幹事長は『これはあくまで論点整理であって、党税調がしっかり対応します』とし、自民党の税制調査会で税制改革の議論を行い、政府税調の論点整理どおりの『サラリーマン増税ありき』を否定しました」。こう書いています。
そのうえ「同幹事長は『誠に私も遺憾なことだと思っています。私から財務省に厳しく注意しました』としたうえで、『いずれにしても新聞の見出しだけを見て判断しますから、「サラリーマンの増税路線」という見出しが出ましたが、そういうことではありません』と明確に否定しています」と書いています。
今度の法案は、自民党・幹事長が主張していたことと、まったく違うことをやろうとしています。
これは、明確な公約違反です。だれが見てもはっきりしています。
 じっさいに「定率減税の全廃」でどれだけ増税になるでしょうか。
じっさいに「定率減税の全廃」でどれだけ増税になるでしょうか。
夫婦子ども2人の4人世帯のばあい、年収500万円で3万5000円、年収600万円で5万6000円、年収700万円で8万2000円の増税になります。
また、独身の場合、それぞれ7万6000円、13万5000円の増税です。
まさにサラリーマンを直撃する大増税です。これを、公約違反で国民に押しつけるなどとんでもないことです。
国税庁による国税OB税理士への顧問先斡旋・天下り問題について
 次に、国税庁による国税OB税理士への顧問先斡旋・天下り問題についてききました。
次に、国税庁による国税OB税理士への顧問先斡旋・天下り問題についてききました。
国税OB税理士というのは、23年以上税務署に勤務して研修を受ければ、税理士の資格が取得できるというものです。
税理士には、「試験組」と「OB組」の2種類あるといわれています。
全国の税理士のなかで、OB税理士の割合は、全国で約6万8642人の税理士のうち、約2万2945人。3分の1を占めています。
退職して税理士を開業することは自由です。
 しかし問題は、OB税理士のなかでも「指定官職」と呼ばれる税務署の正副署長以上、地方国税局の調査部長、局長のばあいです。
しかし問題は、OB税理士のなかでも「指定官職」と呼ばれる税務署の正副署長以上、地方国税局の調査部長、局長のばあいです。
これらの幹部が退職するさい、各国税局の人事課がわざわざ顧問先企業つまりお客さんを組織的に紹介する仕組みがあるのです。
これは、きわめて異常なシステムです。
たとえば、昨年7月の退職者に対して各国税局等がどのように税理士顧問先のあっせんをしているでしょうか。
あっせんをした退職職員の数 359名 (全国計)
1人あたりのあっせん企業数 10.9件 (全国平均)
1人あたりの平均月額報酬 66.0万円(全国平均)
あっせん件数10件以下 171人
あっせん件数20件以下 173人
あっせん件数30件以下 15人
 退職職員一人当たりの平均年額報酬は66万円×12ヶ月=792万円となります。退職職員全ての年額報酬は792万円×359人=28億4328万円です。
退職職員一人当たりの平均年額報酬は66万円×12ヶ月=792万円となります。退職職員全ての年額報酬は792万円×359人=28億4328万円です。
あっせん件数20数件の税理士もおり、年額報酬が1000万円を超える人もいることになります。
驚くべき状況です。年間、約4000近い企業をあっせんしているわけだが、どのようにして、企業を見つけてくるのでしょうか。
東京税理士会の調査で、あっせん・予約の申し入れがあった時の状況についてきいたところ、「税務調査をきっかけとして、その前後に申し入れ等が顧問先にあった」というのが17.4%もあります。
 税務調査をきっかけに申し入れるとなると、まさに押しつけであり権力の乱用です。
税務調査をきっかけに申し入れるとなると、まさに押しつけであり権力の乱用です。
しかも、2年経ったらその企業に次のOB税理士を送り込むというやり方をしています。これが押しつけでなくて、いったい何でしょうか。
東京税理士会が、2004年11月に調査した「税務職員の退職時における業務侵害行為に関する実態調査の集計結果」によると、国税局からあっせん・予約の申し入れがあった時、どのような結果になったかというと、顧問先が受け入れを拒否したのはわずか10.1%にすぎません。
すでに税理士がいるのに、顧問先が受け入れた(2階建てなどになった)というのが84.1%にのぼっています。企業が断れないという実態が浮き彫りになっていません。
なぜ、こんなあっせんをする必要があるのでしょうか。
 今年の1月27日、全国青年税理士連盟が国会議員への申し入れ「聖域なき構造改革を推進するために国税職員の天下りの廃止を強く要望します」があります。
今年の1月27日、全国青年税理士連盟が国会議員への申し入れ「聖域なき構造改革を推進するために国税職員の天下りの廃止を強く要望します」があります。
そこには、以下のように書かれています。
1、国税職員の天下りは、国税OB税理士と税務職員の癒着をもたらします。
国税職員の天下りとは、国税OB税理士が国税局から税理士顧問先のあっせんを受けることを言います。その根拠は民間の需要に対応することにあるというのが、政府の見解です。
しかし、民間が高い報酬を支払ってでも国税職員の天下りを受け入れる理由は、税務行政の便宜を図ってもらうためです。また、東京国税局幹部クラスのOB税理士はほとんど税務調査を受けない聖域とされてきた事は、国税OB税理士と税務職員の癒着をしめすものです。
2、国税職員の退職後の生計扶助を民間に押し付けるのは間違っています
国税職員の天下りは、退職勧奨の代償というのが政府見解です。
しかし、これは、実質的には、国税職員の天下りを通じて、早期退職により国家が支給すべき退職金を肩代わりすることと同じです。
国税職員の天下りは、まさしく国家の責任を民間に転嫁させることを意味するものです。
現在、確定申告の真っ最中です。政府は「納税者の誤解を招かないように」といっていながら、こんなことを続けています。
確定申告で中小企業は、大変な思いをしています。その一方で、国税局が組織的に斡旋を行いOB税理士1人で何百万円という報酬をもらっているのです。こんなやり方は、直ちにやめるべきです。
私の質問に対して、谷垣財務大臣は「国民の疑惑を受けないよう、そのつど見直しをする」と述べました。