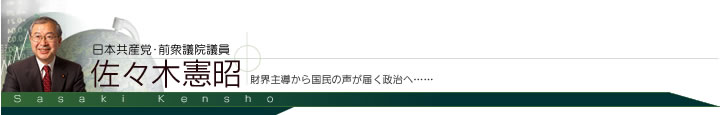奮戦記
【04.02.29】巨額の国債増発は、経済と暮らしに何をもたらすか?
 「世界一の借金王になっちゃった」と言ったのは、故小渕元総理でした。
「世界一の借金王になっちゃった」と言ったのは、故小渕元総理でした。
しかし、その後も国の財政赤字が増え続けています。
一昨日の財金委で議論された法案は、赤字国債発行をもとめるものです。
この法案によって発行される赤字国債発行は30兆900億円、国債依存度は44・6%と、当初予算としては過去最悪を記録するものとなります。
歳入のほぼ半分を借金でまかなうというのですから、異常な財政運営であることは明かです。
これによる国債発行残高は483兆円にのぼり(04年度末)、その大きさはほぼGDPの規模に匹敵します(対GDP比96%程度)。
国・地方合わせた長期債務残高は719兆円で、対GDP比で言えば、143.6%(いずれも04年度末)となります。
 OECDベースでいえば、対GDP161.2%で、米、英、独、仏の50〜70%と比べても飛びぬけて悪いのです。
OECDベースでいえば、対GDP161.2%で、米、英、独、仏の50〜70%と比べても飛びぬけて悪いのです。
政府は「改革と展望」が示すように、この巨額の政府債務を社会保障費等の歳出削減と増税によって乗り切ろうとしており、国民負担増は避けられません。
そのうち市中発行分は、114.6兆円(発行総額の約7割)ということです。
さらに2005年度以降は、過去の景気対策のために出した国債の借換債の発行が急増します。
現在は潤沢な資金のもとで金融機関も大量に国債を消化していますが、景気が回復に向かうと消化難が表面化する恐れがあります。
 いまのところ、日銀は金融の量的緩和政策のもとで、長期国債の買い切り額を増やし、現在毎月1.2兆億円を買い切っています。
いまのところ、日銀は金融の量的緩和政策のもとで、長期国債の買い切り額を増やし、現在毎月1.2兆億円を買い切っています。
しかしその日銀も、デフレが克服されれば、超低金利政策から脱却するとしています。
そうなれば、現在のような国債買い切りを続けるわけにはいかなくなるのではないでしょうか。
「改革と展望」では、デフレからの脱却時期を06年度としています。それは、まさに国債の大量償還=借換債の増発の時期と重なります。
日銀が超低金利政策を続ければインフレが避けられず、逆に超低金利政策をやめ長期国債の買い切り額を減らせば、国債の暴落(長期金利の上昇)の危機が現実化します。
いずれにしても、不気味な暗雲が日本経済全体に低くたれこめているのです。

.