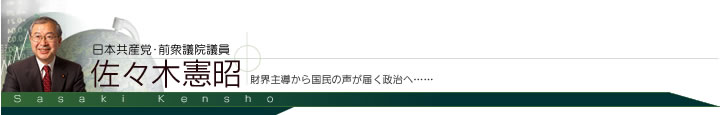奮戦記
【02.09.16】またしても「不良債権処理の加速」だって?
 小泉首相は、「不良債権処理を加速せよ」と柳沢金融大臣や竹中経済財政大臣に号令をかけたと言います。昨日のことです。
小泉首相は、「不良債権処理を加速せよ」と柳沢金融大臣や竹中経済財政大臣に号令をかけたと言います。昨日のことです。●「不良債権処理」はブッシュ米大統領への公約
またしても「不良債権の早期最終処理」! ――いったい、どこまで倒産と失業を増やしつづけるつもりなのでしょうか。これしか、経済政策の「手」は思い浮かばないのでしょうか。
もともとは、小泉首相がブッシュ米大統領との首脳会談で、「不良債権処理を加速させる」と公約したことが発端です。
アメリカに約束したことは、何があってもすべてに優先する――この姿勢が露骨にあらわれています。
不良債権処理をめぐっては、13日、柳沢金融大臣と会談したハバード米大統領経済諮問委員会(CEA)委員長も、「金融システムの問題が日本の成長の足かせになっている」と指摘、問題の早期解決を促したといいます。●「税金投入」「借金棒引き」……何でもありか!
 自民党の山崎幹事長は、整理回収機構(RCC)による不良債権の実質簿価買い取りを主張し、自民党デフレ対策案に盛り込みました。――これは簡単に言えば、銀行のために不良債権を高く買ってやり税金で穴埋めするというものです。
自民党の山崎幹事長は、整理回収機構(RCC)による不良債権の実質簿価買い取りを主張し、自民党デフレ対策案に盛り込みました。――これは簡単に言えば、銀行のために不良債権を高く買ってやり税金で穴埋めするというものです。
速水優日銀総裁も、9日の諮問会議でRCCの買い取り価格引き上げにふれました。いったい日銀は、なぜこのような政策に便乗するのでしょう。
これに悪のりした竹中経済財政大臣も、「公的資本注入が必要だ」などと主張しています。
これにたいし柳沢金融大臣は、「不良債権処理は着実に進んでいる」との認識を示し、公的資金投入に慎重な姿勢を示す一方で、大口不良債権の1年以内の最終処理などを着実に実施する考えを表明したそうです。
最終処理の方法には、法的整理、債権放棄、整理回収機構(RCC)への売却があります。このうち、大口不良債権の債権放棄などを活用した私的整理は、借金の棒引きにあたります。
なぜ、大企業にたいして借金棒引をきするのに、中小企業からは厳しく取り立てるのでしょう。――「中小企業・業者の借金こそ棒引きしてほしい」。これが、庶民の率直な声ではないでしょうか。●減らせば減らすほど、増える
 10の不良債権のうち3減らせば残りは7。さらに7を減らせば残りはゼロ。
10の不良債権のうち3減らせば残りは7。さらに7を減らせば残りはゼロ。
――どうも小泉総理などの頭のなかには、このような考え方があるように思います。
しかし、これがいかに単純で現実離れしているか、経済の実態を見れば明らかです。
<柳沢金融大臣>
たとえば、日銀が8月に発表した「全国銀行の2001年度決算」によると、129の銀行の不良債権処理額は、9兆7000億円(前年比59.0%増)でした。
では、残高は減ったでしょうか。不良債権残高は、前年度に比べて3割も増え43兆2000億円に達してしまったのです。
いったい、なぜでしょうか。
不良債権処理とは、中小企業にとっては資金の回収(貸しはがし)にあうということです。貸しはがしにあった多くの中小企業は、倒産・廃業に追い込まれ失業者も増えます。連鎖倒産もおこり、当然、消費も冷え込みます。
そうなれば、他の中小企業も経営が悪くなって不良債権がまたまた増える。……これが経済の実態なのです。●20万社から30万社がつぶされる
 私は、昨年5月28日の衆議院予算委員会で、小泉内閣の掲げるような「不良債権早期最終処理」をおこなえば、「少なくとも20万から30万社の中小企業が不良債権処理の対象になる」と指摘しました。
私は、昨年5月28日の衆議院予算委員会で、小泉内閣の掲げるような「不良債権早期最終処理」をおこなえば、「少なくとも20万から30万社の中小企業が不良債権処理の対象になる」と指摘しました。
これは、年間の企業倒産件数(約1万8000件)の10倍以上にあたるのです。
金融庁などの資料をもとにしたこの試算にたいし、柳沢金融相は「データを持ち合わせていない」とのべるにとどまり、試算を否定することはできませんでした。
この質問を、当時の夕刊紙「日刊ゲンダイ」(01年5月31日付)が、「大手銀行の不良債権処理で中小企業は断末魔」「倒産30万社、失業者150万人の戦慄(せんりつ)データ」「救われるのは大企業だけではたまらない」と、大きくとりあげました。
関連リンク●不良債権を優良債権に変えてこそ
 では、どうすればいいのでしょうか。
では、どうすればいいのでしょうか。
「急がば回れ」です。――いまは不良債権でも、将来は立派な優良債権に変わる。このような明るい展望がもてるようにするのが政治の役割でしょう。
そのため、最終消費市場が拡大するような政治、家計消費が上向くような政治が、いまこそもとめられているのです。
日銀の「生活意識に関するアンケート調査」(今年4月)でも、それははっきりしています。「あなたはどうすれば支出を増やしますか」という問いに対して、こう答えています。……
第一は「雇用や収入の不安の解消」
第二は「消費税率の引き下げ」
第三は「国民負担の将来像の明確化」
第四は「所得税減税」でした。
この国民の要望に応えるのが、政治の役割ではないでしょうか。
これまでのような大銀行やゼネコン応援の政治とは、まったく正反対の家計応援の新しい政治こそ求められているのです。
.

.
こまったもんですな〜
はあ!