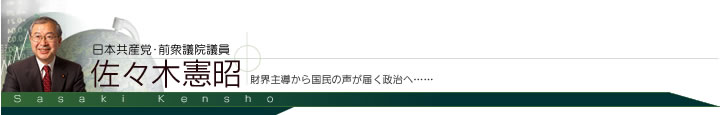2003年02月24日 第156回 通常国会 予算委員会≪経済問題等集中質疑≫ 【188】 - 質問
銀行の手数料いっせい値上げ 政府の金融政策が原因
2003年2月24日、予算委員会で、小泉総理が出席して経済問題についての集中質疑がおこなわれ、佐々木憲昭議員は、銀行による手数料いっせい値上げの問題をとりあげました。
佐々木議員は、質問の冒頭、小泉総理にたいし「東京三菱銀行にいって、両替機で100円玉1枚を1円玉100枚に両替すると、いくら手数料がかかると思うか」とたずねました。佐々木議員が、「200円もとられる」と言うと、小泉総理は驚き、「正常な手数料だと思うか」との問いに、「これはおかしいと思うのも無理ない」と答えました。
2月17日から、東京三菱銀行では、行内に設置している両替機の利用を有料化し、50枚を超える両替にたいし一律200円の手数料を徴収しはじめました。UFJ銀行や三井住友銀行も有料化を検討しています。商売をしていれば、釣り銭のための両替は日常的に必要です。佐々木議員が「零細業者は、ギリギリのところで営業をやり生活している。こういう人たちの声も聞かないで、いきなり手数料を取り立てる。優越適地位の乱用だ。あまりにも一方的ではないか」と追及すると、小泉総理も「どうして、こちらは安い手数料ですから来て下さいという銀行が出てこないのか」と銀行を批判しました。
手数料の値上げは両替だけではありません。土曜日の午前から昼間にかけてのATM(現金自動預け払い機)の利用を有料化する動きが、UFJ銀行を皮切りに大手銀行のなかであいついでいます。また、残高証明書の発行手数料、通帳などの再発行、当座小切手用紙交付、手形用紙交付の手数料など、手数料の値上げラッシュが続いています。
公正取引委員会は、佐々木議員の質問にたいし、土曜日昼間のATM料金の有料化について、都銀大手4行などからヒヤリング調査を開始していることを明らかにし、「調査結果を踏まえてきちんと対応していきたい」と答えました。
手数料値上げの一方で、預金者は大変な低金利を強いられています。預金金利は、90年代を通して下がり続け、現在では0.003%に達しています。100万円預けても利息は30円しかつきません。土曜日にATMを1回利用したら、3年分の利子がいっぺんに吹き飛んでしまいます。1992年度には都市銀行は、預金者に対する利息の支払いに、11兆4130億円を費やしていましたが、2001年度には1兆2631億円にまで下がっています。
一方、手数料収入を示す「役務取引等収益」は、1992年度には経常収益の3.1%にすぎませんでしたが、2001年度には9.5%へと3倍以上になっています。この増え方は、小泉内閣になってから激しくなっています。
佐々木議員は、「預金者の怒りは当然だ」と批判し、総理の認識を問いました。小泉総理は、「自分は値上げしません、これだけ安いですと宣伝する金融機関が出てこないことが不思議だ」と答弁しました。
これに対し、佐々木議員は、「小泉内閣が不良債権を短期間で一気に処理させようとしてきたことが、銀行の収益追求に拍車をかけている」と手数料値上げを引き起こしている政府の金融政策を批判。加えて、政府が、公的資金の注入銀行に提出させている「経営健全化計画」のなかで手数料収入を増やす計画を立てさせ、金融庁が承認していることをとりあげ、これを是正するように求めました。
手数料値上げを政府が奨励する仕組みを指摘されたにもかかわらず、竹中金融担当大臣は、「公的資金を入れている以上、一定の枠をはめている。あとは個々の経営判断だ」と銀行経営者の問題だと答弁しました。
佐々木議員は、「中小企業にたいする貸し出し目標は全然達成できない。それで手数料だけはどんどん上げてくださいと計画を出させて超過達成している。こんなデタラメな金融行政はない」と政府の姿勢を批判しました。
議事録
○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
私は、銀行の手数料の問題についてお聞きをしたいと思います。
週刊ダイヤモンドが行ったアンケートでは、8割の人が、銀行のサービスに不満がある、こう回答しておりまして、そのトップが、各種手数料が高い、これが一番多いわけで、26%でありました。
まず初めに、具体的な問題で総理にお聞きをしたいと思います。
小泉総理は銀行に行って両替をするなんということはないんだろうと思うんですけれども、例えば、東京三菱銀行に総理が行きまして、両替機で100円玉を1円百枚に両替する。この場合、手数料は幾ら取られると思いますか。
○小泉内閣総理大臣 私は両替したことないから、幾ら取られるか知らないんです。
○佐々木(憲)委員 正直なお答えですけれども、100円を1円玉に両替しまして1円玉100枚にしますと、手数料は200円取られます、200円。これは正常な手数料だと思いますか。
○小泉内閣総理大臣 何ですか、100円を両替するのに200円取られる。これは、おかしいと思うのも無理ないと思いますね。
○佐々木(憲)委員 それはもうそのとおりで、おかしいんですよ。おかしいことがまかり通っているんです、今。
例えば東京三菱銀行、これは1週間前からこれを始めたんです、こういうことを1週間前から。2月17日から、どんな金額でも、50枚を超える両替を行えば、1回について一律200円取るということであります。例えば1000円を1円にかえる、1円玉を1000枚ですね、それでも200円取られる。すべて200円。2000円を1円玉にかえても200円取られる。
ですから、私どものところに、ある業者の方からこういう訴えが来たんです。零細なクリーニング屋の店主でございます。1円、2円という商売をしているので、消費税のためにおつりの1円玉が必要です。手数料の200円は、1000円の2割です。いつつぶれるかわからないような零細な業者は、そんな金出せないですよ。あれだけ銀行に税金をつぎ込んでおいて、我々から手数料を取るというのはどういうことですか。もう死ねということですか。私のような零細な者はどこへ両替に行けばいいんですか。
これまで大手銀行は、店内に設置している両替機を使用する際の手数料は無料だったんです、今までは。ところが、200円の手数料を取り始める。これは一つの銀行だけじゃないんですよ。UFJ銀行も、両替機での手数料徴収も検討していく、こう言っているんです。まあ、横並びでやりたいと。三井住友銀行も、有料化について検討していくと。次々と、これは有料化をしていく方針でございます。
このクリーニング業者の声にありますように、商売をしていれば、これはもう当然、つり銭のために両替は日常的に必要なんです。零細業者はぎりぎりのところで営業をやって生活をしているわけでありまして、こういう人たちの声も聞かないで、これはもうともかく決めたら一律に手数料は取り立てると。これは余りにも一方的で、強い者が弱い者から取り立てる、まさに優越的地位の乱用と言わざるを得ないと思うんですけれども、総理、これは一方的じゃありませんか、余りにも。どう思いますか。
○小泉内閣総理大臣 これはおかしいから、うちの銀行はそんなことはやらないという銀行が出てきてもよさそうなものだと思いますけれどもね。
○佐々木(憲)委員 それが出てこないで、次から次と、みんな横並びでやっているんですよ。私が今取り上げたのは両替機の話ですよ、両替機。今まで無料だったんです。つまり、自分で両替に行ってかえるわけですから、ただだったんです、今までは。それが、こういう形で一律に200円。やり始めたら、うちの銀行も私の銀行もといって、全部やり始める、私はこういうのは非常におかしいと思いますよ。
それから、例えば、今両替機の話をしましたが、実は、資料を見ておわかりのように、窓口での両替は既に軒並み有料化されておりまして、このときは住友銀行が先陣を切ったんです、それまでは両替手数料、なかったんですが。その後も大手銀行は次々に有料化していきまして、2000年の10月に住友銀行が有料化しました。翌2001年の5月には東京三菱銀行、7月にはあさひ銀行と三和銀行、8月に富士銀行、9月に第一勧業銀行、こういうふうに続いたわけです。小泉内閣になってから重立った都銀が有料化で横並びをし始めた、こういうことであります。
手数料の値上げは両替だけではありません。資料の1を見ていただきたいんですけれども、ここでも、今までは土曜日の午前中から昼間にかけまして、ATM、これは無料でありました。ところが、それを有料にする動きがUFJ銀行を皮切りに大手銀行の中で相次いでおります。
このような銀行の新たな手数料徴収や手数料の一斉引き上げが近年どんどん行われるようになって、利用者から強い批判の声が上がっているわけであります。
そこで、公正取引委員会にお聞きしますけれども、公取では土曜日のATM有料化をめぐって調査を進めると財務金融委員会や記者会見で述べておられますけれども、これはどのような観点から調査が必要だと判断したのか、公取委員長の答弁を求めたいと思います。
○竹島政府特別補佐人(公正取引委員会委員長) 御指摘のATMの利用手数料の引き上げでございますけれども、公正取引委員会といたしましては、端的に申し上げますと、話し合い等によるいわばカルテル的な行為によってこういうことが行われているのかそうでないのかという基本的問題意識を持って、都銀の大手4行並びに全銀協からヒアリングをしておるところでございます。これから、必要な書類等もいただいた上で、私どもとして、それぞれが独自に判断しているということであれば独禁法上の問題が発生するとは思っておりませんけれども、話し合い等があった場合には、その検討、調査結果を踏まえてきちんと対応してまいりたいと考えております。
○佐々木(憲)委員 調査をしっかりやっていただくということなんですけれども、これは大体もう現象的にもはっきりしているんですよ、これは一斉なんですから、時間が若干ずれてはいますけれども。コストは違うんですよ、それぞれ銀行によって。それが全部同じ金額になる。大体そういうこと自体が私は異常だというふうに思うんです。
いつごろ調査結果が出るんでしょうか。
○竹島政府特別補佐人 先週からヒアリングを始めておりまして、今週さらに資料等の提示を求めるというようなことも含めまして、今月中にそういった一次的な作業が終わると思いますが、その分析、検討を踏まえて速やかに私どもとしての考えをまとめたいと思っております。
○佐々木(憲)委員 では次に、手数料が今どんどん上がっていまして、しかし、預金をしても金利がつかない、こういう状況であります。
何でこうなるのかというのが大変重大でありまして、資料の2を見ていただきますが、預金利息の推移をグラフにしました。90年代にどんどん下がりまして、もう本当にゼロに張りついているような状態で、現在では0・003%と、信じられないような普通預金の金利でございます。
10年前には、100万円を預けますと年で約3000円から4000円ぐらいの利子はつきました。ところが、今は、100万預けても30円、こういう状況であります。その利子も、土曜日にATMを1回利用すると105円取られますから、3年分の利子が消えてしまう、こういうことになるわけでありまして、これはもう、預金者の怒りは当然だと思うんです。
資料3を見ていただきたいんですけれども、右側ですが、これは、都市銀行の金利の支払いの部分について、つまり、預金者に対する利子の支払いですね、92年には、都市銀行は預金者に対する利息の支払いに11兆4130億円を費やしておりました。ところが、2001年度には1兆2631億円と、10分の1に利子の支払いが下がっているわけですね。
これに対して、手数料の収入を示す役務取引等収益というのが左側にありますけれども、それを見ますと、90年代を通じてふえ続けまして、経常収益に占める割合は、92年度の3・1%から9・5%、3倍以上になっております。
この数字が間違いないかどうか、金融庁に確かめておきたいと思います。
○伊藤金融担当副大臣 お答えをさせていただきたいと思います。
今委員御指摘がございましたように、預金利息の額については、92年度11兆4130億円、それが2001年度1兆2631億円で、10兆1499億円の減少でございます。そして、役務取引等収益が経常収益に占める割合でございますが、92年度3・1%が2001年度には9・5%、プラス6・4%でございます。
○佐々木(憲)委員 私が申し上げたとおりの数字で、正確だと思うんですね。
銀行は、一方では利子をどんどん下げまして、下げることによってもうけを上げているわけですよ。他方で手数料をどんどん引き上げてぼろもうけをする。二重に庶民から利益を得ていると言わざるを得ないと思うんですね。
手数料収入というのは特に小泉内閣になってから急増しておりまして、3枚目の表の左側でありますけれども、私はこれは問題だと思うんですね、何でこうなるのかということを後で聞きますが。
ここに挙げたのはごく一部で、一枚目の表を見ていただきたいんですが、先ほど、ATMですとか両替機のところを見ました。下の方を見ていただきますと、こういうふうになっているんです。残高証明書一通当たりの発行手数料は、東京三菱銀行もみずほ銀行も、420円から735円、横並びで引き上げられております。通帳などの再発行は幾らか。1050円だったのが2100円、2倍になっております。それから、当座小切手用紙交付、用紙の交付ですね、小切手用紙を交付されるというだけなんですが、630円だったけれども2100円と、3倍以上ですよ。手形用紙の交付は、1050円だったのが3倍の3150円。
これは、幾らコストがかさむとはいっても、余りにもひどい引き上げ方ではないのか。全体としてはデフレ時代だと言われて、中小業者が大変な、商売で赤字が出ている、そういう必死にやっているときに、もう一方的に決めたということで、これは競争にも何もならないんですよ。まさに優越的な地位の乱用だと思うんですけれども、総理は、こんなめちゃくちゃなやり方はおかしいと思いませんか。
○小泉内閣総理大臣 これは、自分はこんな値上げしません、これだけ安いですと、もっと宣伝するような金融機関が出てきてもよさそうだと思うんですけれども、出ないことが不思議だと思います。
○佐々木(憲)委員 そういうことになっていかないんです、今実際に。自分のところはこんなに手数料は安いですよ、引き下げましたとなぜ出てこないのか。
私は、政府がやはり金融政策の上でそういう事態をつくっているのではないか。つまり、収益性の追求ということを竹中大臣も盛んに主張されるわけですね。小泉内閣になりまして、不良債権を短期で一気に処理しよう、そういう場合には、銀行に収益性を追求せよと盛んにおっしゃるわけであります。
ある新聞は、手数料の値上げの背景についてこう書いています。政府が金融再生プログラムで収益力の強化を促したのを受け、手っ取り早く利益を稼ぎたいという思惑がある、あるいは、不良債権処理損失や貸出先の倒産に備えて積む貸倒引当金の増大は不可避、収益を上げる手段を血眼で探している。あるいはこういうふうに言われている。公的資金注入で収益力の強化が求められやむを得ず踏み切ったというような言い方をしながら、ずっと一斉に手数料だけが上がっているというのが実態であります。
これが背景にこういうことがあるのではないかと思いますが、いかがでしょうか、総理。
○小泉内閣総理大臣 収益を上げるということは大事だと思いますが、値上げすれば収益を上げるというのを全経営者が判断するのは、これはおかしいんじゃないか。ほかの企業を考えてみれば、むしろ値下げして収益を上げている企業はたくさんあるわけですよ。
そういう発想を、いわゆる逆転の発想というか、今までの金融行政じゃなくて、そういう経営者が金融機関にどうしてあらわれないのか。そういう点が、私は、まだ金融機関、努力が足りないんじゃないかと思う点がたくさんあると思いますね。
○佐々木(憲)委員 その逆転の発想が起こらない原因が、実は金融行政の中にあるんです。
例えば、公的資金注入銀行は、経営健全化計画というのを出しますね。それぞれ経営健全化計画を出しております。例えば、ここにありますけれども、三井住友銀行は、役務取引等利益、先ほど言った手数料の利益ですね、これを2004年度末までに607億円ふやして2260億円にするという計画を立てております。金融庁はこれを承認して、つまり各銀行とも手数料を上げていくという計画を金融庁がそれを認め、実際にこの実績は計画を超過達成しているんですよ。これは、全然下げるなどというのは出てくる余地がないんですよ。
大体、経営健全化計画にこういう項目を入れて引き上げるのを奨励するというのは間違っているんじゃないですか。いかがですか、これは。
○竹中金融担当大臣 先ほどから総理がおっしゃっていますように、各行横並びで経営していくということは、私はないと思いますけれども、独自の判断でやっているとは思いますけれども、本当にそういった違った経営判断がやはり出てくるような状況を私はつくりたいと思っております。
佐々木委員が御指摘の経営健全化計画でありますけれども、これは収益、公的資金を入れている以上、それはやはりきちっと経営を健全化してもらわなければいけないわけで、そのために一定の枠をはめているということはあると思います。
しかし、あとどのようにするかというのは、これはあくまでも個々の経営判断であります。その個々の経営判断に優越的な地位の乱用がないように、これは公取でしっかりと監視をしていただく。さらに、競争がさらに促進するような環境を我々としてはつくっていく必要があると思っております。
○佐々木(憲)委員 金融行政で私は非常に重大だと思うのは、中小企業に対する貸し出し目標は全然達成できない。中小企業に対する大変な貸し渋り、貸しはがしをやっておいて、それで手数料だけはどんどん上げてくださいと計画を出させて超過達成している、そんなでたらめな金融行政はない、こうはっきり申し上げて、質問を終わります。
関連ファイル
- 【配付資料1】都銀の手数料値上げの動向(pdf)
- 【配付資料2】預金金利の変化(pdf)
- 【配付資料3】手数料収入と預金利息支払の推移(pdf)