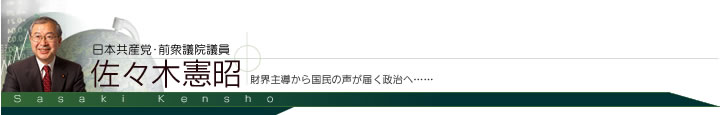奮戦記
【10.04.16】過去の過誤払い──銀行を指導すると副大臣が答弁
 今日の財務金融委員会で、私の質問に対して、大塚耕平金融担当副大臣は盗難された銀行通帳や印鑑などのよる銀行の過誤払いに関して、2006年施行の預金者保護法以前の被害についても「しっかりと対応するよう指導したい」と答弁しました。
今日の財務金融委員会で、私の質問に対して、大塚耕平金融担当副大臣は盗難された銀行通帳や印鑑などのよる銀行の過誤払いに関して、2006年施行の預金者保護法以前の被害についても「しっかりと対応するよう指導したい」と答弁しました。
私がとりあげたのは、2002年に衣料品販売業務代行業者が自宅に保管していたUFJ(=現三菱東京UFJ)銀行の通帳と印鑑を盗まれた事件です。
2002年11月に犯人によって開設された三井住友銀行の口座を経由して預金2800万円が引き出されました。
 UFJ銀行では、担当者が書類の筆跡の違いに気がついたにもかかわらず、上司が振り込みを許可。三井住友銀行は、本人確認も不十分なまま口座を開設し、払い戻しに応じました。
UFJ銀行では、担当者が書類の筆跡の違いに気がついたにもかかわらず、上司が振り込みを許可。三井住友銀行は、本人確認も不十分なまま口座を開設し、払い戻しに応じました。
私は、預金者保護法の附則にも法の施行前の被害について、「法律の趣旨に照らし、最大限の配慮が行われる」と明記されているのに、両行は対応していないと指摘しました。
大塚副大臣は「銀行の社会的責任は大きい」と答弁しました。
NPOバンクは、貸金業規制の枠外に位置づけ支援すべきだ
 私は、6月に完全施行される貸金業法に関して、NPOバンクを対象外とするよう求めました。
私は、6月に完全施行される貸金業法に関して、NPOバンクを対象外とするよう求めました。
多重債務の被害者をこれ以上出さないため、貸金業法を完全施行することは当然ですが、NPOバンクにとって次のような問題がおこります。
(1)貸付業務経験者の確保が義務づけられるが、非営利活動では給与の支払いが困難だ。
(2)指定信用情報機関の信用情報のの使用・提供が義務づけられるが、利用者が住宅ローンや教育資金などを銀行から借りにくくなる。
(3)借入総額が年収の3分の1までという総量規制によって必要な資金が貸せなくなる。
 私は、サラ金会社、アコムの保証を受けることが利用条件となっている三菱UFJ銀行のカードローンなどが総量規制の適用除外となっているのに、NPOバンクが規制されるのは不合理だと強調しました。
私は、サラ金会社、アコムの保証を受けることが利用条件となっている三菱UFJ銀行のカードローンなどが総量規制の適用除外となっているのに、NPOバンクが規制されるのは不合理だと強調しました。
NPOバンクも「指定信用情報機関への加入義務」「総量規制」の適用除外にすべきだと主張するとともに、貸金業法の対象からはずし、NPOバンク法を制定するよう求めました。
亀井静香金融担当大臣は、「零細な金融ニーズに対応することはきわめて大事だ。指摘されたことと同様の意見を持っている」と答えました。
.