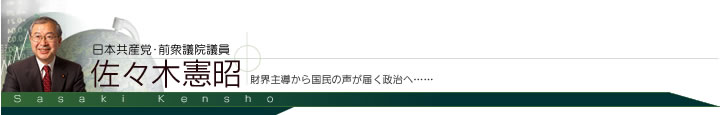奮戦記
【06.09.16】サラ金規制―なぜ例外なき金利引下げを認めないのか
 昨日、自民党が決めた「貸金業法改正案」は、あまりにもサラ金業界やアメリカ寄りの内容に偏ったものとなっています。
昨日、自民党が決めた「貸金業法改正案」は、あまりにもサラ金業界やアメリカ寄りの内容に偏ったものとなっています。
出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法の上限金利水準(年15─20%)に引き下げグレーゾーン金利を撤廃する時期は、おおむね3年先となり、2009年末から2010年の前半となります。
また、焦点となっていた少額・短期の貸出金利の上乗せを認める「特例措置」は、上限金利25.5%、期間2年とされてしまいました。
 なぜ、「すみやかな金利引き下げ」を認めず、「特例措置」を認めるのでしょうか。まったく、なっとくできません。
なぜ、「すみやかな金利引き下げ」を認めず、「特例措置」を認めるのでしょうか。まったく、なっとくできません。
もともと金融庁の「有識者懇談会」は、「特例措置」に大反対だったのです。
その「特例」を堂々と導入したのは、明らかに、サラ金業界とアメリカの圧力によるものです。
サラ金業界の団体、全国貸金業協会連合会(全金連)は、これまで出資法の29.2%という高金利を維持するようもとめてきました。
 全金連の石井会長は「自民、公明、民主、国民新党の各議員に…陳情していく」と述べ、これまでも繰り返し与党の国会議員らに献金を含む政界工作をしてきたのです。
全金連の石井会長は「自民、公明、民主、国民新党の各議員に…陳情していく」と述べ、これまでも繰り返し与党の国会議員らに献金を含む政界工作をしてきたのです。
また、アメリカの金融大手業界団体は、在日米国商工会議所や米国政府の意向を受け、8月に与謝野金融担当大臣に書簡を送り、金利引き下げに反対していました。
貸金業法の改正の目的は、多重債務者を救い、安心して住める社会をつくることにあります。――サラ金業界とアメリカの圧力に屈し、庶民を犠牲にすることは、絶対に認められません。